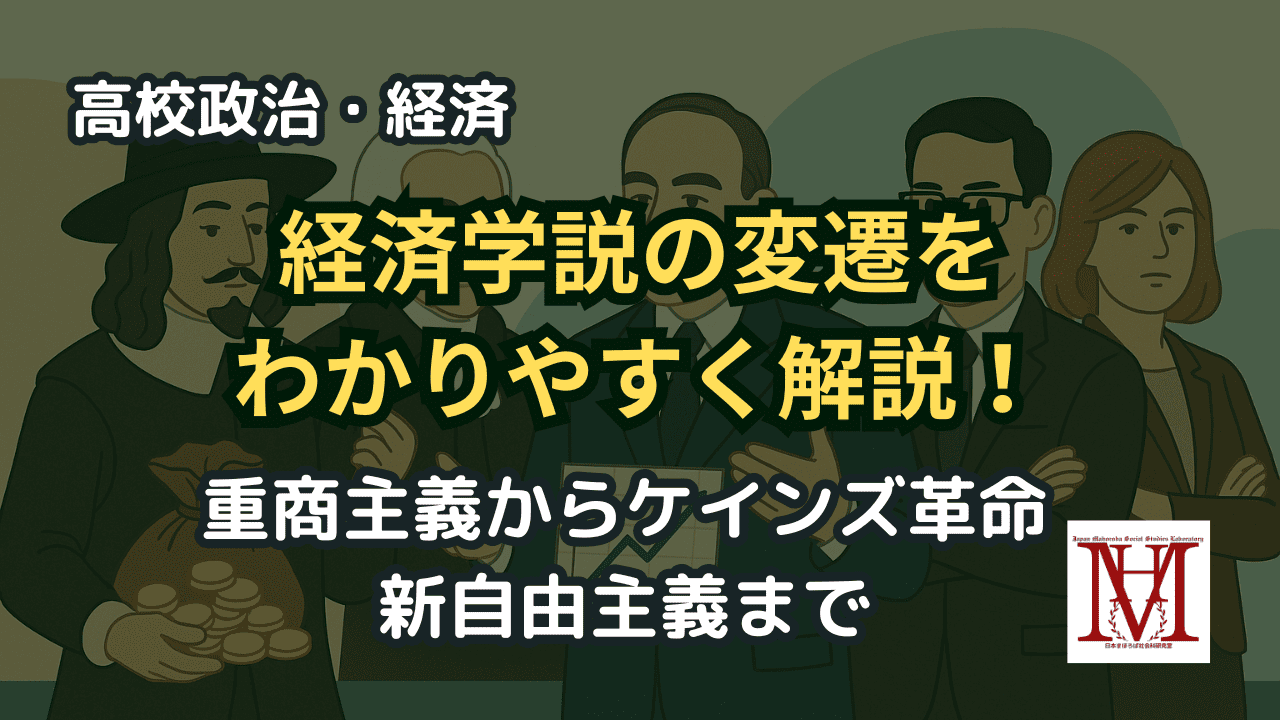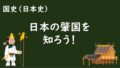経済の歴史を学ぶとき、「どうしてこんなにたくさんの学説が出てくるのだろう?」と思ったことはありませんか。実はそれぞれの経済学説は、時代ごとに人々が直面した課題に応える形で生まれてきたものです。
16世紀のヨーロッパでは国王の力を強めるために重商主義が登場し、18世紀には自由を重んじる古典派経済学が現れました。その後も、産業革命による貧富の差の拡大に対抗して社会主義が広がり、世界恐慌の克服にはケインズ経済学が大きな影響を与えました。そして20世紀後半には、新自由主義やグローバル化の議論が展開されていきます。
この記事では、こうした経済学説の流れを 「なぜその理論が登場したのか」 という視点から、高校政治経済の学習範囲に沿ってわかりやすく解説していきます。
重商主義(mercantilism)
16世紀から18世紀にかけて、ヨーロッパ各国では絶対王政が確立し、国王は軍事力や官僚機構を整備して権力を強化していきました。その際に財源を確保する手段として経済に国家が積極的に介入し、国家の富を増やすことを目的とした考え方が重商主義です。重商主義では、国家の富は金や銀といった貴金属にあると考えられ、それをどれだけ国内に蓄積できるかが国力の強さを示すとされました。
この考え方には二つの系統があり、スペインでは植民地から金銀そのものを獲得する重金主義が展開され、一方のイギリスでは輸出を増やし輸入を抑えることで貿易差額によって金銀を取り込もうとする貿易差額主義が主流となりました。イギリスの経済思想家トーマス・マンはこの立場を代表しています。
重商主義のもとでとられた政策は、輸入品に高い関税をかけて国内産業を守る保護貿易政策や、国王と結びついた特権商人に貿易の独占を認める仕組み、さらに植民地を原料供給地かつ製品市場として利用する植民地政策などでした。これらはいずれも国家と商人が一体となって富を確保しようとする特徴を持っています。これらは歴史的に見ても、東インド会社のような特許会社の設立や航海法による他国船の排除などにも見られ、国家と商人が一体となって富を蓄積しようとした特色を持っていました。
重商主義は国際貿易を飛躍的に発展させ、のちの産業革命を準備する役割を果たしました。しかし同時に、植民地の維持に多大なコストがかかり国家財政を圧迫したり、特権商人だけが利益を独占して経済のゆがみを生じさせたり、国家の過度な介入によって市場の自由な発展を妨げたりするという問題も抱えていました。こうした点が批判を呼び、次に登場する重農主義へとつながっていきます。
重農主義(physiocracy)
18世紀のフランスでは、重商主義の保護貿易政策に対する批判が高まりました。そうした中で登場したのが重農主義であり、代表的な経済学者はフランソワ・ケネーです。重農主義の基本的な立場は、農業こそが唯一新たな富を生み出す産業であり、商業や工業はすでに存在する富を形を変えるだけであるというものでした。
この考え方に立てば、農業が発展すればそれを土台にして工業や商業も発展していくとされ、国家は経済に過度に介入すべきではないと主張されました。重農主義の思想家たちは「自由放任主義(レッセ=フェール)」を掲げ、市場に任せれば自然な調和が生まれると説きました。
ケネーも「aissez faire, laissez passer(なすに任せよ、行わせておけ)」という言葉を残しており、経済活動を自然の秩序に委ねよという意味で、絶対王政下の統制経済への強い批判の意味を持ちました。この発想はのちの資本主義経済の基本原理である自由競争につながっていきます。
重農主義は農業のみを生産的産業とする点では今日の視点から見れば誤りを含んでいますが、経済活動における「生産」と「流通」の区別を理論的に整理したことは重要な意義を持ちました。そして何よりも、国家が経済を管理する重商主義とは対照的に、市場に自由を与えることを重視する姿勢は、アダム・スミスらの古典派経済学へと橋渡しする役割を果たしました。
古典派経済学の登場
18世紀から19世紀にかけてのイギリスでは、重商主義による国家の経済統制に対する批判が高まっていました。その流れの中で登場したのが古典派経済学です。古典派経済学は自由放任と自由競争を重視し、国家の過度な干渉を否定する立場をとりました。その中心人物が、のちに「経済学の父」と呼ばれる アダム・スミス です。
アダム・スミスの思想
アダム・スミス(1723–1790)は、1776年に刊行された『国富論(諸国民の富)』で世界的に知られています。彼はその中で「労働こそが富の源泉である」とする 労働価値説 を提唱しました。これは、国の富は金銀や交易の差額ではなく、人々の労働によって生み出されるものであるという考え方でした。この立場は重商主義を根本から批判するものでした。
さらにアダム・スミスは、経済活動において国家が積極的に介入する必要はなく、人々が自由に経済活動を行えばよいと考えました。人間は基本的に利己的な存在であり、「もっと利益を得たい、もっと豊かになりたい」という欲求に突き動かされて行動します。スミスは、この利己心こそが社会全体を発展させる原動力になると考えました。
このとき重要な役割を果たすのが「神の見えざる手」という比喩です。各人が自分の利益を追求して行動しても、その結果として社会全体の調和が自然に生まれるという考え方です。市場の自由競争の中で、誰かが利益を得ようとすれば、それが商品の供給や価格の調整をもたらし、結果として社会全体に利益が行き渡るのだと説明しました。
アダム・スミスの理想とする国家像は、経済活動に過度に干渉せず、必要最小限の役割にとどまる「小さな政府」「安価な政府」でした。国家は治安維持や司法の整備など最低限の役割を果たせばよく、それ以上は市場に任せるべきだとしました。
このような国家観は、19世紀ドイツのラッサールによって「夜警国家」と批判されます。つまり「国家は夜間に治安を見張る夜警程度の存在にすぎない」という揶揄です。
それでも当時のアダム・スミスの思想は、成立したばかりの資本主義的市民社会を楽観的にとらえ、市場の自己調整機能を信頼するものでした。彼にとって重要なのは、他人に迷惑をかけない限り各人が自由に行動できる社会であり、その自由こそが社会を豊かにするという確信でした。
リカード – 比較生産費説(比較優位の理論)
アダム・スミスが「労働価値説」や「見えざる手」によって古典派経済学の基礎を築いた後、その理論をさらに徹底して展開したのが デイヴィッド・リカード(1772–1823) です。彼は代表的著作『経済学および課税の原理』において、アダム・スミスの考えを引き継ぎつつ、より理論的に体系化しました。
リカードが唱えた最大の功績は、国際貿易の理論である 比較生産費説(比較優位の理論) です。彼は分業の考え方を国内にとどめず、国際的な規模に拡張しました。
ここで、リカードが説明した比較生産費説について、イギリスとポルトガルという二国を例に説明します。まず、イギリスとポルトガルの特色を説明すると以下の通りです。
- イギリス:工業が発展し、特に「毛織物(ウール製品)」の生産に優れています。また、ワインも生産できるけれど、気候が冷涼でブドウ栽培に不利なため効率は悪い。
- ポルトガル:温暖な気候に恵まれ、ブドウからの「ワイン」生産が得意。一方で、毛織物を作る工業はイギリスほど発達していない。
両国とも、理論的には「毛織物」も「ワイン」も作れるのですが、それぞれ得意度に差があります。
- イギリス:毛織物が特に得意、ワインは苦手
- ポルトガル:ワインが得意、毛織物は苦手
このとき、イギリスは毛織物に特化して輸出し、ワインはポルトガルから輸入する。逆にポルトガルはワインを輸出して毛織物をイギリスから輸入する。するとお互いに得意分野に集中できるので、両国の生活水準がともに上がるというわけです。
数字で説明してもわかりやすいと思います。以下の数字は、「労働者100人あたりの生産量」を仮定して、イギリスとポルトガルが毛織物とワインを作った場合の得意・不得意を表したものです。
| 国 | 毛織物(反) | ワイン(樽) |
|---|---|---|
| イギリス | 100 | 40 |
| ポルトガル | 60 | 120 |
自給自足を行った場合、イギリスは毛織物もワインも作れますが、ワインは40樽しかできません。ポルトガルも両方作れますが、毛織物は60反しか作れません。つまり両国が「何でも自分で作る」やり方をすると、お互いに「得意ではないもの」を無理に作ることになり、効率が悪くなってしまいます。
他方、
- イギリスは毛織物を作るのが圧倒的に得意です(100反)。
- ポルトガルはワインを作るのが圧倒的に得意です(120樽)。
という条件から、
イギリスは毛織物の生産に集中し、ワインはポルトガルから輸入します。逆にポルトガルはワインに集中し、毛織物はイギリスから輸入します。すると、両国は自分の得意なものを多く作れるようになり、それを交換することで、どちらの国も豊かになります。
この理論の面白いところは、たとえイギリスの方が毛織物もワインも両方「絶対的に得意」だったとしても、相対的により得意な分野(毛織物)に集中した方がよい、という点です。これを「比較優位」といいます。なぜかというと、イギリスがワインを自国で作ろうとすると、本来なら毛織物を作るのに使えた労働力や資源をワインに振り分けなければなりません。ところがイギリスはワインの生産効率が低いため、毛織物ほど大きな成果は得られません。つまり、ワインを作ることで「もっとたくさん作れたはずの毛織物」を失うことになるのです。
この「他の選択をした場合に得られたはずの利益を失うこと」を機会費用といいます。イギリスにとってワインを作る機会費用は「失われた毛織物の生産量」であり、これはとても大きいのです。
一方で、ポルトガルは毛織物よりもワインを効率的に作れるため、ワイン生産の機会費用は比較的小さい。だからイギリスは毛織物に集中し、ポルトガルはワインに集中することで、お互いに得意分野でより多くの成果を出し、それを貿易で交換すれば、両国とも自給自足のときより豊かになれるのです。
この考え方は「同じ産業であっても相対的に得意な分野に特化し、そうでないものは輸入すべきだ」というものです。リカードはこうして 自由貿易 を理論的に正当化しました。
リカードの自由貿易論は、当時「世界の工場」と呼ばれたイギリスだからこそ成立した理論でした。圧倒的な工業力を背景に、自国に有利な国際分業体制を築こうとする「強者の理論」と言えます。
確かに理論としては合理的ですが、現実にはいくつかの問題点が指摘されます。相手国は自国の産業育成を断念せざるを得ず、発展途上のまま取り残される危険があります。また、イギリス国内でも特定産業を放棄した場合、その分野で働いていた労働者は失業の危機に直面します。つまり比較生産費説は「理論的には正しいが、社会的には多くの困難を伴う」考え方だったのです。
リカードはまた、当時のイギリスで行われていた穀物輸入制限政策である 穀物法 に反対しました。彼は自由貿易を重視する立場から、保護貿易的な政策を批判したのです。この点で、食料供給の制約を重視するマルサスと論争を繰り広げました。
マルサスの人口論
トマス・マルサス(1766–1834)は『人口論』によって有名です。彼は人口と食糧の増加速度の違いに注目しました。食糧の生産量は「1, 2, 3, 4, 5」といった算術級数的な増え方をすると考えたのに対し、人口は「1, 2, 4, 8, 16」といった等比級数的に増えていくと主張しました。つまり、人口の増加スピードが食糧の増加を常に上回るため、長期的には飢餓や貧困が避けられないというのです。
もちろん「食糧を輸入すればよいのではないか」という反論もありましたが、マルサスはそれだけでは根本的な解決にはならないと考えました。人口増加の圧力は社会の持続的な課題であり、貧困の原因は単なる政策不足ではなく人口と資源の構造的な関係にあると位置づけたのです。この議論は、その後の経済学に「人口問題」を組み込む重要な契機となりました。
J.S.ミルの経済学と功利主義
19世紀に活躍したジョン・スチュアート・ミル(1806–1873)は、『経済学原理』という本を著した思想家です。彼はアダム・スミスやリカードの「労働価値説」を受け継ぎながらも、それを少し発展させ、経済学を「人間の幸福と結びつけて考える学問」としてとらえようとしました。
ミルは、経済学者であった父ジェームズ・ミルの厳しい教育を受けて育ちました。また、父の親友であり「功利主義」を唱えたジェレミ・ベンサムからも強い影響を受けています。功利主義とは「最大多数の人が最大限に幸せになることを社会の目標にすべきだ」という考え方です。
このような影響を受けたミルにとって、経済学は単に「お金や生産をどう効率よく扱うか」だけの学問ではありませんでした。むしろ、人間社会全体の幸福を大きくするために役立つ学問であるべきだと考えたのです。そのため、アダム・スミスのように「市場にまかせれば自動的にうまくいく」と楽観的に考えるのではなく、市場の働きを信頼しつつも、そこに「正義」や「分配の公平さ」を加えて考えようとしました。
古典派経済学の限界
アダム・スミス、リカード、マルサス、ミルと続いた古典派経済学は、いずれも18〜19世紀のイギリスを舞台に展開されました。その基本は「自由競争を基盤にした資本主義社会の原理」を理論化することでした。しかし、この体系にはいくつかの限界もありました。
まず、リカードの比較生産費説においても指摘されたように、自由貿易は理論的には合理的でも、現実には国内の失業問題を引き起こし、他国の産業発展を阻害する危険をはらんでいました。また、マルサスの人口論は貧困の構造的原因を示しましたが、景気変動や失業問題などの突発的な経済危機への対応は十分に考慮されていませんでした。
つまり、古典派経済学は「市場が自由に働けば社会は調和する」という理念を掲げながらも、現実に発生する不況や失業には無力だったのです。この欠点がやがて新しい経済学派を生み出す契機となり、19世紀後半以降の経済思想はさらなる展開を迎えることになります。
フリードリヒ・リスト – 歴史学派の特徴
19世紀のドイツでは、イギリスの古典派経済学に対抗する形で 歴史学派 と呼ばれる経済思想が登場しました。その代表的人物の一人が フリードリヒ・リスト(1789–1846) です。歴史学派の基本的な立場は、「経済の法則は普遍的なものではなく、各国の歴史的・社会的状況によって異なる」というものでした。つまり、イギリスの経済学者が「自由競争はどの国にも当てはまる普遍的原理だ」と説いたのに対し、歴史学派は「過去の事例を見れば、同じ理論をすべての国にそのまま適用することは危険である」と警告したのです。
リストは著書『経済学の国民的体系』において、歴史的な実例を引きながら「過去にこうした政策をとった国は失敗した」と具体的な事例を提示し、国ごとの経済発展段階を踏まえた経済政策の必要性を訴えました。
リストの大きな貢献は、経済発展段階説 に基づく保護貿易論でした。彼は経済発展にはいくつかの段階があり、それぞれの段階ごとにふさわしい政策が存在すると考えました。
イギリスの古典派経済学は「自由貿易こそが普遍的原理である」と主張しましたが、リストはそれを批判しました。なぜなら、当時のドイツはまだイギリスのように産業革命を達成していない後進国であり、比較生産費説に従って自由貿易に参加すれば、自国の未発達な産業は壊滅してしまう危険があったからです。
リストは「幼稚産業保護論」を唱え、後進国は自国の産業が成熟するまで保護貿易政策によって守られるべきだと主張しました。イギリスがすでに圧倒的な工業力を持ちながら「さあ、自由に競争しよう」と呼びかけることに対し、「それではドイツは一方的に不利な立場に追い込まれてしまう」と批判したのです。
リストの主張は、リカードの比較生産費説が「強者の理論」であることを鋭く突きました。イギリスのような先進国にとって自由貿易は有利ですが、後進国にとっては自国の産業が育たず、永遠に従属的立場に置かれてしまう危険があります。リストは「発展段階に応じた経済政策」を提唱し、歴史的事例を踏まえて警告しました。
こうしてリストを中心とするドイツ歴史学派は、自由放任を普遍原理とするイギリス古典派経済学に対して、「国ごとの歴史や発展段階を無視してはならない」という相対的・具体的な視点を提示しました。この考え方は、後の保護貿易政策や国家主導の産業育成策の理論的基盤となり、19世紀後半以降のドイツ経済発展に大きな影響を与えました。
社会主義の登場と展開
社会主義思想の出発点
資本主義は自由競争を基盤に発展しましたが、その結果として「勝ち組」と「負け組」の格差が広がり、労働者は厳しい状況に置かれるようになりました。こうした資本主義の矛盾に対するアンチテーゼ(対抗思想)として登場したのが社会主義です。社会主義は「結果の平等」を重視し、労働者が搾取されず人間らしく生きられる社会を目指しました。
16世紀のトマス・モアの『ユートピア』や17世紀のベーコンの『ニューアトランティス』は、理想社会を描いた先駆的な思想でした。これらは「ユートピア(どこにも無い理想郷)」を描いたものであり、後の社会主義思想の原点の1つとされています。
空想的社会主義と科学的社会主義
18~19世紀には、資本主義社会の不平等に挑もうとする試みとして「空想的社会主義」が登場しました。フランスのサン=シモンは産業者を中心とした理想社会を構想し、イギリスのロバート・オーウェンはアメリカで「ニューハーモニー村」という理想的共同体を創ろうとしました。またフランスのフーリエは「ファランジュ」と呼ばれる協同組合的な理想郷を考案しました 。しかし、これらの試みは現実的な実現力に欠け、資本主義を根本から変える力にはなりませんでした。そのため、マルクスとエンゲルスは彼らの思想を「空想的社会主義」と批判しました 。
これに対し、マルクスとエンゲルスが提唱したのが「科学的社会主義」です。マルクスは大著『資本論』で資本主義の矛盾を科学的に分析しました。彼は「労働こそが価値の源泉であり、資本家の利益(利潤)は労働者が生み出した価値の一部を賃金として支払わず搾取することで生まれる」と論じています 。この理論(労働価値説・剰余価値説)は、「資本家の儲けは労働者から搾取した不払い労働の成果だ」という考え方です 。マルクスはこの搾取をなくして人間らしさを取り戻すためには、生産手段を私有から公有に移し、社会主義(共産主義)による計画経済に移行することが必然だと考えました。
革命と社会民主主義
マルクスは「労働者階級(プロレタリアート)は資本家階級(ブルジョワジー)との矛盾によって必ず階級闘争を起こし、やがて革命に至る」と予測しました。彼とエンゲルスが1848年に発表した『共産党宣言』でも、「歴史は階級闘争の歴史であり、資本主義の矛盾は最終的にプロレタリア革命をもたらす」と主張されています 。この思想に影響を受けて、実際に20世紀には1917年のロシア革命(レーニンによるソビエト政権の成立)や、1949年の中国革命(毛沢東による中華人民共和国の成立)が起こりました。これらはマルクスの理論を現実化したもので、後にマルクス=レーニン主義とも呼ばれます。
一方、イギリスやフランス、ドイツなどの先進国では、19世紀末から20世紀にかけてマルクスの予想したような革命は起きませんでした。労働者の生活水準は徐々に向上し、労働者はすぐに武力蜂起するよりも議会で権利拡大を求める道を選んだのです。こうして流れていったのが「社会民主主義」です。ドイツのベルンシュタインはマルクス主義を修正し、「暴力革命ではなく議会を通じて少しずつ社会を改良すべきだ」と主張しました (修正マルクス主義)。またイギリスではウェッブ夫妻やバーナード・ショーらが参加したフェビアン協会が「議会による漸進的な改革」を目指し、急進的な革命よりも民主的手段での社会主義実現を唱えました 。彼ら社会民主主義者は「少しずつでも議会立法によって社会を改善すること」を重視し、福祉国家の基礎を築いていきました。
近代経済学の登場 ― ケインズ革命
世界恐慌とニューディール政策
西暦1929年(昭和4年)10月24日、アメリカ・ニューヨークのウォール街で株価が大暴落しました。この「暗黒の木曜日(ブラックサーズデー)」をきっかけに、世界を巻き込む大不況――世界恐慌が始まります。失業者があふれ、各国の工場や銀行が次々と倒産しました。
当時のアメリカ大統領であった共和党のフーヴァーは「市場は自然に回復する」として有効な対策を打てず、不況はさらに悪化しました。そこで西暦1933年(昭和8年)に就任した民主党のフランクリン=ルーズベルト大統領は、思い切った政策転換を打ち出します。これが有名なニューディール政策(新規まき直し政策)です。
ニューディール政策の内容は多岐にわたりました。例えば、公共事業で雇用を作り出したり、農業生産を調整して価格を安定させたり、労働組合を保護したりするなど、さまざまな取り組みが行われました。また、失業保険や年金制度といった社会保障制度も整備され、国民生活の安心を守る仕組みがつくられました。
- 全国産業復興法(NIRA):産業部門ごとに政府が生産や価格を調整し、賃金や労働時間の規制も行った
- 農業調整法(AAA):農産物の生産を制限し、価格を守るために農家へ補助金を支給
- テネシー川流域開発公社(TVA):ダム建設などの公共事業を行い、雇用を創出すると同時に地域開発を推進
- ワグナー法:労働組合の権利を守り、労働者の立場を強化
- 社会保障法:失業保険や年金制度を整え、国民生活の安全網をつくる
これらは、政府が積極的に「有効需要」を作り出して不況を克服しようとする取り組みとして、ケインズ理論を先取りした実践例だと評価されます。ただし、ニューディール政策がすぐに恐慌を解決したわけではありません。失業率は1930年代後半まで高止まりし、一部の政策は「政府の市場介入が行き過ぎ」として違憲判断を受け、中断されたものもありました。
そういったこともあり、アメリカ経済が完全に不況から立ち直ったのは、第二次世界大戦による軍需拡大が大きな要因だったという見方もあります。
つまり、ニューディール政策の評価は二つに分かれます。
- 「恐慌からの脱出を決定づけた」と見る意見
- 「恐慌克服の決定打ではなく、大戦が本当の転換点だった」とする意見
しかし多くの研究者は、ニューディールが資本主義の崩壊を防ぎ、政府が経済に積極的に関与する「大きな政府」路線を定着させた点で、歴史的な意義が非常に大きかったと言われています。
ケインズ革命と「大きな政府」
この時代に登場したのが、イギリスの経済学者ジョン・メイナード・ケインズです。ケインズは西暦1936年に代表作『雇用・利子および貨幣の一般理論』を発表し、それまでの古典派経済学を根本から批判しました。
古典派経済学は「市場は放っておけば自動的に調整され、失業もやがて解消される」と考えていました。しかしケインズは「市場任せでは不況は長引き、失業者は救われない」と主張しました。そこで打ち出したのが有効需要という考え方です。
有効需要とは、「単に欲しいと思う潜在的な需要」ではなく、「実際にお金を払ってモノやサービスを買う需要」のことです。ケインズは「不況のときには政府が公共事業や財政支出で有効需要を作り出せば、景気は回復し、完全雇用も実現できる」と説きました。
この考えは、それまでの「政府は小さい方がよい」という自由放任主義と正反対でした。そのため、経済学における大転換としてケインズ革命と呼ばれるようになったのです。ケインズの理論は、各国が公共事業や福祉による積極的な景気対策を採用する理論的な土台となりました。
[参考] アメリカ以外の世界恐慌への対応
世界恐慌はアメリカだけでなく、世界各国にも広がりました。
イギリスやフランスなど植民地を多く持つ「持てる国」は、植民地を利用してブロック経済を築きました。たとえばイギリスは1932年のオタワ会議で自治領との間に特恵関税協定を結び、ポンドを基軸にしたスターリング=ブロックを形成しました。フランスもフランを基軸にしたフラン=ブロックを作りました。ブロック経済とは、植民地や親しい国々を含む閉じた経済圏をつくり、内部では関税を下げ、外部からの輸入には高関税をかける仕組みです。
一方、ソ連はスターリンの下で五か年計画による計画経済を進めており、世界恐慌の直接的な打撃をほとんど受けませんでした。海外資本に依存せず、国内で重工業化と農業集団化を進めていたためです。外から見ると「資本主義が混乱する中で、社会主義国ソ連だけが安定している」と映り、一時的に「社会主義の優位性」が強調されることになりました。もっとも実際には、国内では強制労働や粛清などの暗い側面も進んでいたのですが…。
現代経済学 ― ケインズから新自由主義、そしてグローバル化へ
前述のように、ケインズ経済学は大恐慌を乗り越えるうえで大きな力を発揮し、各国は「大きな政府」による景気対策を行いました。アメリカのルーズベルト大統領のニューディール政策はその象徴でした。
しかし、この「大きな政府」による修正資本主義にもやがて限界が訪れます。
スタグフレーションと新自由主義の登場
1970年代、オイルショック(石油危機)が二度(1973年、1979年)起こり、世界はスタグフレーションという新たな難題に直面しました。スタグフレーションとは、景気停滞を意味する「スタグネーション(Stagnation)」と物価上昇を意味する「インフレーション(Inflation)」を組み合わせた合成語で、不況(景気停滞・失業)が続く中で物価上昇(インフレ)も起きてしまう現象です。通常は不況なら物価は下がるはずですが、石油価格の高騰がそれを覆し、「不景気なのに物価高」という事態が各国で起きました。これは、従来のケインズ経済学では対処が難しい問題でした。ケインズ理論は需要不足の不況に政府支出で需要を足す発想でしたが、同時にインフレも起きている状況では効果が上がりにくかったのです。
そこで登場したのが「小さな政府」を掲げる新自由主義(ネオリベラリズム)です。新自由主義はケインズ政策への批判から始まりました 。市場の自律性を重視する経済学者フリードマンら(シカゴ学派)は、「政府による裁量的な財政出動は景気を安定させるどころか悪影響も生む。政府の役割は最小限にし、市場メカニズムに任せるべきだ」と主張しました 。彼らは特に通貨供給量を一定ルールで管理するマネタリズムを唱え、ケインズ流の大規模財政出動は批判しました 。「市場の失敗」を矯正しようとする政府介入よりも、「政府の失敗」のほうがかえって深刻だとフリードマンは指摘しています 。このような新自由主義経済学は、1970年代後半から80年代にかけて各国の政策に影響を与えました 。
新自由主義を政策に取り入れた代表例が、1980年代の イギリスの「サッチャー政権」とアメリカの 「レーガン政権」です 。イギリスのサッチャー首相やアメリカのレーガン大統領は「小さな政府」を掲げ、規制緩和や国営企業の民営化、福祉予算の削減などを断行しました 。日本でも中曽根康弘首相(在任1982~87年)が行政改革を進め、日本国有鉄道の民営化などを行っています(いわゆる「民活」「民営化」路線)。彼らの政策は、いずれも政府の関与を減らし市場の自由に任せるという点で共通していました。これは景気対策に需要側(ディマンドサイド)を重視したケインズ派に対し、供給側(サプライサイド)を重視するアプローチでもありました。規制緩和で企業活動を活発化させ、減税で投資意欲を高め、経済の供給力を伸ばすことで成長させようとしたのです。
アンチ・ケインジアンの経済学者たち
1970年代以降、ケインズ理論への批判や見直しが進む中で、様々な角度から資本主義経済を分析する経済学者たちが登場しました。彼らはいずれも「政府が経済にどの程度介入すべきか」という単純な論点だけでなく、資本主義そのもののあり方や社会全体の公正さに目を向け、現代経済学の多様な姿を形作っていきました。主な人物とその考えを以下に紹介します。
オーストリア出身のシュンペーターは、資本主義の本質は「創造的破壊」にあると説きました。企業家が新技術や新しい発想で古いものを破壊しながら経済は発展すると考えたのです 。シュンペーターはこのイノベーションのダイナミズムを資本主義の原動力と位置づけました。一方で彼は著書『資本主義・社会主義・民主主義』(1942年)で、資本主義は「その成功ゆえに自壊する」と予言しました 。つまり大企業が台頭して安定志向になると新しい挑戦が減り、知識人層も資本主義批判を強めるため、最終的に資本主義は活力を失って衰退するという見方です。シュンペーターのこの資本主義没落論は当時「敗北主義」とも批判されましたが、彼自身は現実を冷静に分析した結果だと反論しています。
次に、先ほども紹介したアメリカのフリードマンです。彼は、ケインズの「政府が需要を作り出すべき」という考えに真っ向から反対した経済学者です。フリードマンは「政府は経済に手を出しすぎず、通貨供給量の調整だけに専念すべきだ」と主張し、マネタリズム(通貨数量政策)を提唱しました 。彼は特に「政府の失敗」の弊害を強調し、「市場の失敗より政府の失敗の方がはるかに深刻である」と述べています 。これは、景気対策で政府があれこれ介入するよりも、かえって問題を悪化させる危険が大きいという指摘です。フリードマンの思想は自由市場を絶対視し、政府の役割を極小化する点で新自由主義の理論的支柱となりました 。
次に、カナダのガルブレイスを紹介しましょう。彼は1950~60年代の豊かなアメリカ社会を観察し、「依存効果」という概念を提唱した経済学者です。彼は著書『ゆたかな社会』(1958年)で「現代の消費者の欲望は生まれつきのものではなく、広告や宣伝によって作り出されている」と分析しました 。企業が商品を売るために巧みな広告で欲望を植え付け、需要そのものを生み出しているという指摘です 。この依存効果によって人々は必要以上にモノを欲しがらされ、大量生産・大量消費が正当化されているとガルブレイスは批判しました。彼の主張は現代の広告産業や消費社会を鋭く言い表したもので、豊かさの中に潜む歪みを突いたものです。
また、アメリカのスティグリッツは、行き過ぎた市場主義やグローバル化がもたらす不公正を批判した経済学者です。2001年にノーベル経済学賞を受賞した彼は、2002年の著書『グローバリゼーションとその不満』でIMF(国際通貨基金)やアメリカ主導のグローバル経済政策を厳しく批判し注目されました 。スティグリッツは、貿易自由化・金融自由化の名の下に推し進められたグローバル化が、結果として世界各地で格差を拡大させていると指摘しています 。特に途上国に対して画一的な市場開放を迫る「ワシントン・コンセンサス」の政策は、貧困層にしわ寄せが行くと批判しました。彼は「市場任せではなく、公平なルールづくりが必要だ」と訴え、世界銀行のチーフエコノミストだった経験から、グローバル経済の中で政府の果たすべき役割を強調しています 。
インド出身のアマルティア・センは、貧困や福祉の問題に人間の「自由」の観点からアプローチした経済学者です。ノーベル経済学賞受賞者のセンは、財や所得だけでは人々の幸福や自由は計れないと考え、「ケイパビリティ・アプローチ」(潜在能力アプローチ)を提唱しました 。彼によれば、人間には本来様々な潜在能力(ケイパビリティ)があり、それを発揮できるかどうかが重要だというのです。例えば一定の収入があっても、教育や医療の機会がなければ自分の可能性を実現できず「本当の意味で自由」ではありません。センは各個人が「自分が価値を置く生き方を選択できる自由」こそが大切だとし、その自由を社会が保障すべきだと説きました 。貧困対策についても、単に所得を与えるだけでなく、教育・医療など能力を引き出す環境づくりが必要だと主張しています。
以上のように、これらの経済学者たちはアプローチこそ異なりますが、いずれも資本主義経済の問題点に新たな光を当てました。彼らは「政府vs市場」という単純な二項対立を超えて、技術革新や社会構造、世界規模での公平性など、経済をめぐる多角的なテーマに取り組んでいます。ケインズの登場以後、現代経済学がさらに多様な問いを追求していることが分かります。
金融自由化とグローバル化
1980年代以降、世界では金融市場の自由化が加速しました。各国で金利や為替の規制が緩和され、巨額の資金がボタン一つで国境を越えて動く時代が到来しました。金融の自由化により、投資機会が増えて大きな利益を得ることも可能になりましたが、その反面バブル(資産価格の行き過ぎた高騰)が生まれては崩壊するリスクも高まりました。実際、1997年のアジア通貨危機や2008年のリーマン・ショック(世界金融危機)は、国際金融市場で膨らんだバブルがはじけて起こった世界的な経済危機でした。金融がグローバルに繋がった結果、一国の金融問題が瞬く間に世界中へ伝播するようになったのです。
また1990年代から2000年代にかけては、いわゆるグローバル化が急速に進みました。トヨタやパナソニックといった多国籍企業が生産拠点や販売網を世界中に広げ、資本(お金)や労働力(人)が国境を越えて移動するのが当たり前になっていきます。世界の国々は貿易や投資で相互に依存を深め、一つの地球経済とも言える状況が生まれました。グローバル化は各国に安い製品や成長の機会をもたらしましたが、その裏で国内の経済構造にも大きな変化を及ぼしました。
日本の場合、1990年代以降のグローバル化で企業が生産拠点を次々と海外へ移転しました。その結果、国内の製造業の雇用が減少し、残った職場でも正社員ではなく派遣社員や契約社員など非正規雇用が増えていきました。かつて安定した職に就いて中間層を形成していた人々が減り、所得格差の拡大が社会問題化しました。いわゆる「格差社会」という言葉が取り沙汰されたのもこの頃です。「努力すれば豊かになれる」と信じられていた社会で、努力しても不安定な生活から抜け出せない人が増えたのです。
こうした格差拡大に警鐘を鳴らしたのが、フランスの経済学者トマ・ピケティです。ピケティは「資本主義はこのままでは必ず格差を広げてしまう」と主張しました。その根拠として提示した有名な不等式が 「r > g」 です 。ここで r は資本収益率(資本から得られる利益の成長率)、g は経済成長率(所得全体の成長率)を意味します。ピケティによれば、歴史的に見て常に r(お金持ちが運用で得る利益)の方が g(全体の成長率)より高い傾向があります 。つまり「資本を既に持っている人」が運用益によって富を増やすスピードの方が、「労働で稼ぐ人」の収入の伸びより速いというのです 。この状態が続けば、資産家はますます豊かになり、資産を持たない人との格差は雪だるま式に拡大していきます。
ピケティは莫大な歴史データを分析し、18~20世紀の長期にわたってこの r > g の関係が成立していたことを示しました。そして「このままだと19世紀のような大格差社会に戻ってしまう。そうならないためにはグローバルな富裕層への課税や富の再分配が必要だ」と提言したのです 。彼の著書『21世紀の資本』(2013年)は世界的なベストセラーとなり、資本主義社会における格差問題にこれまで以上の注目が集まるきっかけとなりました。ピケティの分析は賛否を呼びましたが、「金持ちは金持ちであるだけでますます富み、格差は放っておけば拡大する」という結論 は多くの人に衝撃を与え、各国で経済格差是正策の議論を活発化させました。
まとめ
以上、近代から現代までの経済学説の変遷を概観しました。
経済思想や政策は時代の課題に応じて変化してきました。歴史を振り返ると、経済の在り方について様々な考え方が生まれ、衝突し、また新しい折衷が模索されていることが分かります。
私たちが生きる現代もまた過渡期にありますが、これまでの流れを学ぶことで、より良い社会の方向性を考えるヒントになるでしょう。