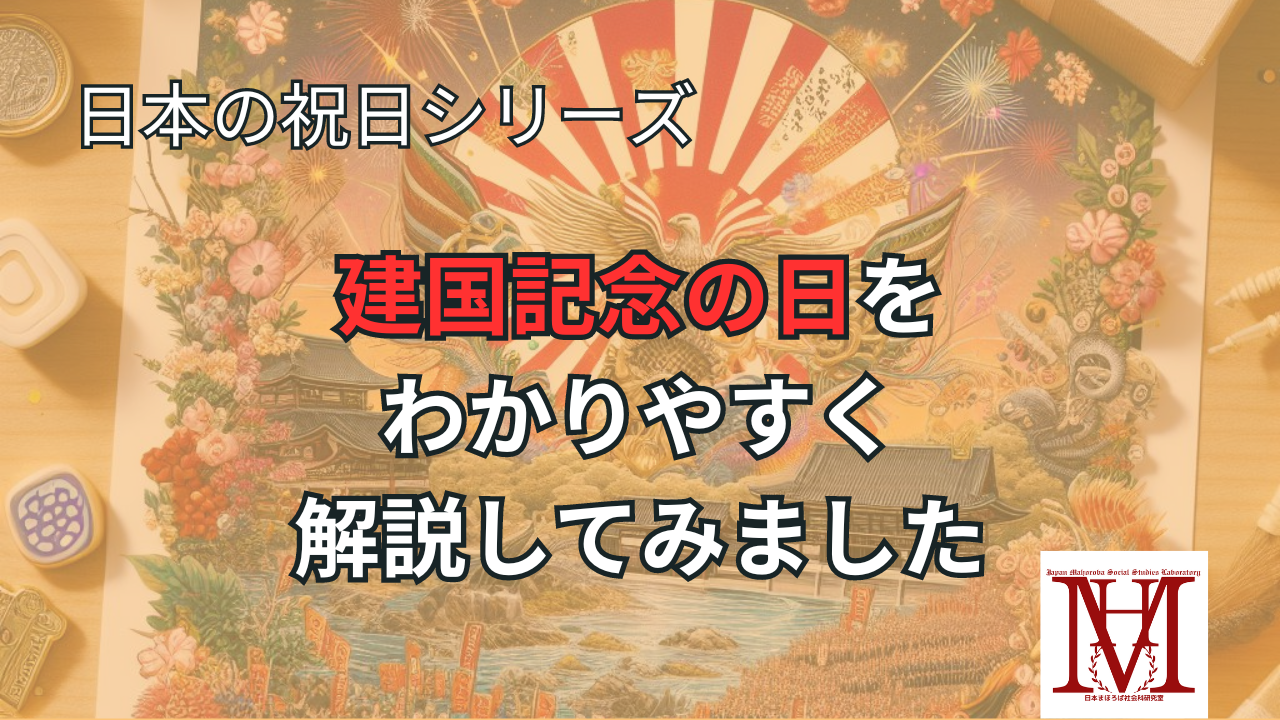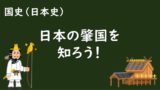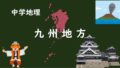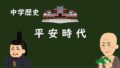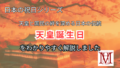皆さん、2月11日は何の日かご存知ですか?
この日は「建国記念の日」として、日本の建国を祝う日です。今回は、この「建国記念の日」について、その歴史的背景や意味を詳しく見ていきましょう。
なお、この記事は船橋市内の小学校で校長を務めていらっしゃり、「日本が好きになる!歴史授業」の名プロデューサーの渡邉尚久先生のお話を参考に作成いたしました。
建国記念の日の由来
「建国記念の日」は、日本の初代天皇である神武天皇が即位したとされる紀元前西暦660年1月1日を現在の暦に換算し、2月11日としたことに由来します。
『日本書紀』によれば、神武天皇は橿原の地で即位し、「日本を家族のような国にしよう」という「即位建都の詔」を渙発されました。
この日が日本の肇国の日とされ、のちに「建国記念の日」として祝われるようになりました。
2月11日、これはただの休日ではなく、日本にとって特別な日であり、国民の祝日として法律で定められている日です。この日は「建国記念の日」であり、「建国をしのび、国を愛する心を養う」日です(「国民の祝日に関する法律」より)。
「建国記念の日」は、日本がどのようにして成立したのか、どのように始まったのかを思い起こす日です。しかし、多くの人々が、日本がいつ、どのように肇国されたのか?また日本国がどのような理念のもとで肇国された国なのかを具体的に知らない人が多いのが現状だと思います。
日本の「建国記念の日」について
日本の肇国 – 世界で一番古い国
神武天皇の前は、神話の時代になります。神話でなければ説明できないぐらい日本の歴史は古いのです。
ところで、初代の神武天皇はどのような国づくりを行おうとお考えになったのでしょうか?日本の肇国の理念を一緒に学んでいきましょう。
神武天皇は「即位建都の詔」で以下のような内容を仰ったとされます。
「辛酉の年の3月1日に、私は東征を行ってから橿原の地に着くまでに6年経過しました。私は神々のお力を借りながら抵抗する勢力を倒してきました。しかしながら、私の力は国の端っこまで及んでおらず、まだ戦乱状態が続いていて、まだ残っている敵たちはなお手強いのですが、私の治める国(橿原を中心とする近畿地方のこと)は平穏に治まっています。そこで、国の中心となる皇居を作ってまいります。しかるにいま、私は日本の国を始めるにあたっての苦しみに直面しています。国民はまだ文明化していません。国民は動物であるかのように巣や穴に住んでいて、生活風習は神々の時代から進歩していないのです。そこで、御神勅に掲げられた理想を受け継いだ者が国のリーダーとなるべきなのです。時間がかかったとしてもこの理想は多くの人々に理解してもらえるはずです。国民にとって利益になることであれば、どうして私が行う政治に妨げが起こるのでしょうか。そこで、山林を切り拓いて皇居を造り、謹んで皇位に即いて、国民が平穏無事に生活できように邁進してまいります。上は天つ神からお授けくださった理想に応えて実現させる国づくりをし、下は邇邇芸命が目指した御心を広めようと思います。その後、国を1つにまとめて都を新しく作り、我が国をみんながともに平和に暮らせる家族が集う家のようにしていきます。これはとても素晴らしいことではありませんか。見渡せば、畝傍山の東南の橿原の地が国の中でもステキな場所なので、ここを国を治める場所に定めましょう。」
拙稿「日本彫刻の精神って言えますか? – 神武天皇の「即位建都の詔」を読む」 (日本まほろば社会科研究室)
この「辛酉の年」というのを計算すると、西暦に換算すると紀元前660年になるのだそうです。あまりにも古すぎます。現存する世界の約200の国の中で、最も古い国が日本であり、次に古いデンマークでさえ、日本とは1000年近くの差があります。さらに驚くべきことに、一つの王朝が途切れることなく、代々続いているのも日本だけです。
みんなが共に平和に暮らせる家族が集う家のような国
ってとても素晴らしい理念だと思いませんか?
なお、詳しい日本の肇国の歴史(神話)については以下のコンテンツで学ぶのがオススメです。
ちなみに、ここでは意図的に「肇国」という用語を使っています。「肇国」と「建国」の言葉の意味はよく似ていますが、重大なところで意味が異なります。
詳しくは、国語WORKSの松田雄一先生の解説動画をご覧ください。大変分かりやすくまとめてくださっている動画です。
「建国記念の日」の現在とその歴史
このように神武天皇が「即位建都の詔」を渙発されましたが、そこから天皇陛下が国づくりのバトンを受け渡していきながら我が国の歴史も繋がってきました。現在の天皇陛下は第126代にあたります。
現在のように国をあげて「国民の祝日」としてこの日を定めたのは明治時代に入ってからでした。明治新政府は明治5年(西暦1872年)にこれまでの太陰太陽暦から太陽暦を採用することを決め、翌年に明治6年(西暦1873年)に正式に太陽暦(新暦)でこの日を「紀元節」と定めました。先の大戦の前までは「紀元節」という名称でした。
しかし、戦後、アメリカが天皇陛下と国民のつながりを恐れ、祝祭日を廃止しました。それにもかかわらず、日本人の8割以上がこの紀元節を復活させたいと考え、その結果、「紀元節」から「建国記念の日」に名称が変更され、昭和41年(西暦1966年)に国民の祝日として認められ、翌年の昭和42年から現在に至るまで続いています。
外国の建国と比較してみよう!
それでは、ここで他国の建国と比較してみましょう。アメリカ合衆国は西暦1776年に建国され、フランスは西暦1789年、カナダで西暦1867年、中華人民共和国は西暦1949年、ロシアは西暦1991年にそれぞれ建国されています。これらの国々と比較すると、日本は先ほども述べたように紀元前660年です。
他の国々では、建国を記念する日を盛大に祝います。例えばアメリカでは、毎年7月4日に独立記念日を祝い、花火が打ち上げられます。カナダでもイギリスから自治権を獲得した日を「カナダ・デー」として、花火が上がり、家族や友人と一緒にお祝いをします。
しかし、日本では、政府主催のお祝いはなく、国民もただの休日としか思っていない人がほとんどです。非常に嘆かわしい状況なのです。
望ましい「建国記念の日」の過ごし方は?
自分の国のことをしっかりと知り、感謝の念を持つことは重要です。
橿原神宮であればベストですが、近くの神社にお参りをするのもよいのでしょうし、特別な行事に参加しなくても、日本の歴史についての本を読んだり、親子で日本の歴史に関する博物館に出かけたりすることもお祝いの1つです。家に国旗を掲揚するのも1つだと思います。
また、日本がお米の国であることから、特製おむすびを配布してお祝いしている神社もあります。
マジメにやらなくても、日本を祝して飲み会や家族でパーティーをやるのもよいでしょう。ケーキにロウソクを立ててお祝いするのもよいでしょう。
ちなみに、戦前に存在した「紀元節」には、学校に登校して講堂に集まり、奉安殿に収められている天皇皇后両陛下の御真影を出してきて教育勅語を唱えたり紅白のお饅頭をいただいて帰宅したとのことです。
建国記念の日は、日本に生まれ、日本の国民であることを誇りに思う日です。それぞれの人が自分なりのお祝いの仕方でこの日を過ごすことで、これまで日本を繋いできた先祖への感謝と、これからの日本への期待が繋がっていくのではないでしょうか。これからの日本がこの先も日本であり続けられるかどうかは、私たち一人ひとりにかかっています。
みんなでお祝いしましょう!