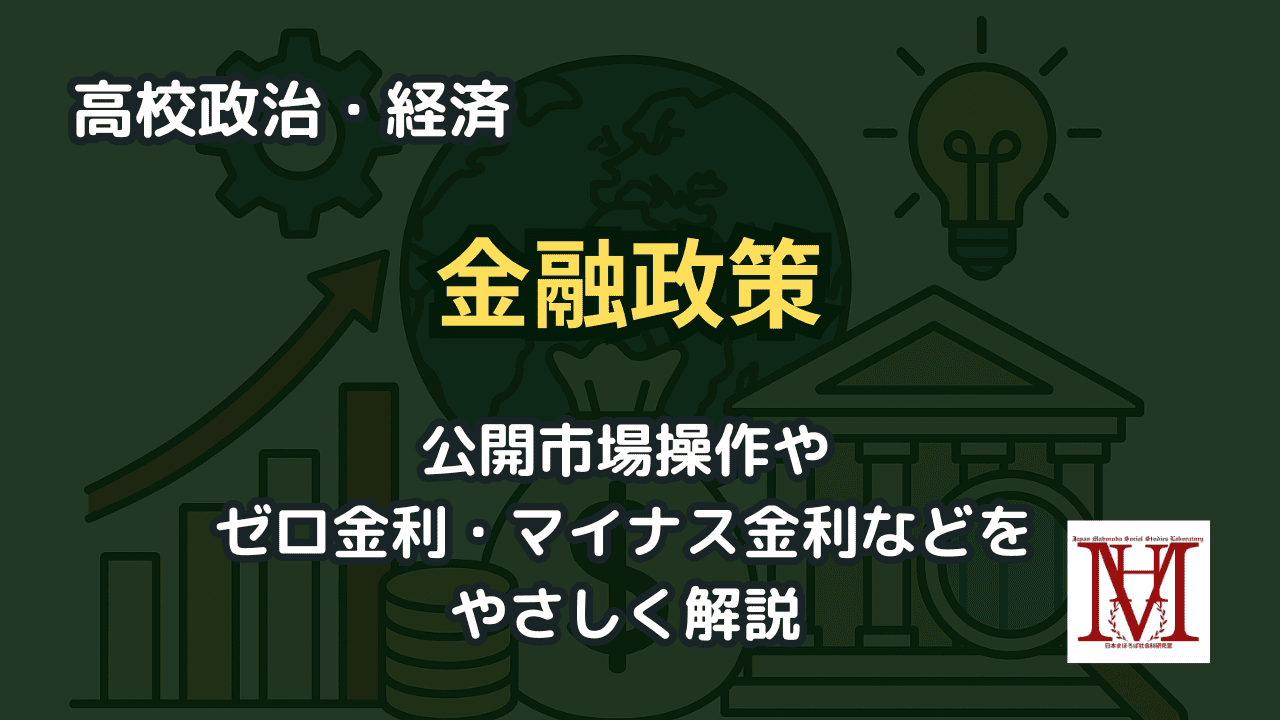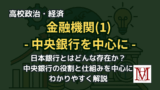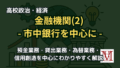私たちが暮らす社会には、目に見えないけれど絶えず動き続ける“流れ”があります。おにぎりの代金が電子マネーで支払われる瞬間も、アルバイト代が口座に振り込まれる夜も、そこには静かにお金が行き交っています。
その流れが速すぎても、遅すぎても、社会は不安定になります。物価が上がりすぎれば暮らしは苦しくなり、逆に物価が下がり続ければ企業は元気を失います。
この揺れをそっと押さえ、経済の鼓動を整える役割を担っているのが、日本銀行の「金融政策」です。社会全体の体温を、熱が出れば冷まし、冷えれば温める──そんな静かな調整の技術なのです。
日本銀行の役割を復習したい人はこちらをご覧ください。
それでは概観していくことにしましょう!
金融政策の中心にある「公開市場操作」
公開市場操作とは、日本銀行が金融市場で国債などの債券を売買し、短期金利や通貨量を調整する政策です。専門的には「直接的調整」であり、「量的金融政策」と位置づけられています。名前は少し堅苦しいですが、やっていることは「お金の出入りを調節する」という、とてもシンプルで力強い作業です。
そして日本銀行は、この公開市場操作を通じて、市場金利――とりわけ政策金利の中心であるコールレート――を望ましい方向へと導こうとしています。
コールレートとは何か?(政策金利の中心)
実は西暦1994年(平成6年)に金利が自由化されるまでは、金融政策といえば「公定歩合」が主役でした。しかし自由化以降、その役割は 無担保コール翌日物金利(コールレート) に移りました。これは、銀行同士が短期間でお金を貸し借りする際につく金利です。市場の資金の動きがもっとも敏感に表れる金利であり、今日の日本における「政策金利の中心」になっています。
コールレートが下がれば、お金は世の中に出やすくなり、上がれば引き締まります。コールレートが低いということは、銀行同士が短期間のお金を借りるときの「利息が安い」状態です。そうすると、銀行にとってはお金の調達コストが下がり、その分だけ企業や家計への貸し出しが増えていきます。設備投資がしやすくなり、住宅ローンの金利も下がり、社会全体にお金の流れが生まれていきます。景気を「温める方向」で働くのが、コールレートが低いときの姿です。
他方、コールレートが高くなるということは、銀行同士が借りるお金の「利息が重くなる」状態を表します。銀行も高いコストを払ってまで貸し出すことは控えるため、企業の投資も落ち着き、ローンの金利も上がります。その結果、市場に流れるお金はゆっくりになり、物価の上昇も抑えられていきます。結果として、景気を“冷やす方向”で働きます。
しかし日銀はコールレートそのものをコントロールすることはできません。そこで日銀は、コールレートを望ましい方向へ導くために、市場に出回るお金の量そのものを動かします。これが、公開市場操作です。
公開市場操作には、日銀が保有する国債などを売却して市場から資金を吸収する「売りオペ」と、市場から国債などを購入して資金を供給する「買いオペ」があります。
以下、もう少しくわしく解説をしていきます。
公開市場操作の中身1: 買いオペレーション ──通貨の流れを「前へ押し出す」政策
買いオペレーションとは、日本銀行が市場から国債を買い取り、その代金として新しいお金を金融市場に送り込む政策です。国債が日銀の手に移り、市場にはそのぶん現金が増えます。
簡単なイメージを紹介します。
たとえば、市中銀行Aが10億円ぶんの国債を持っているとします。そこへ日本銀行が次のように告げます。
「その国債、10億円で買い取りましょう。」
取引が成立した瞬間、起きているのは次の二つの動きです。
まず、日銀のコンピュータが銀行Aの口座に「+10億円」と数字を書き加えます。この数字の上書きが、まさに新しいお金が世の中に出回る瞬間です。
次に、銀行Aは手元の国債を日本銀行に渡します。銀行の資産は、
国債(動きにくい資産)→ 現金(貸し出しに使える資産)
へと姿を変えます。
こうしてお金が増えれば、市中銀行Aは企業への融資に踏み出しやすくなり、家計もローンを利用しやすくなります。こうして資金の流れが徐々に前へ進み、物価も、景気も、少しずつ上向いていきます。
景気が冷え込み、物価が下がり続ける「デフレ」のときに、流れを止めないよう、社会に息を吹き返すために行われる政策が買いオペレーションです。
公開市場操作の中身2: 売りオペレーション ──過熱しすぎた流れを「ひと息つかせる」政策
売りオペレーションはその逆で、日銀が手元の国債を市場に売り出し、その代金として市場のお金を回収する政策です。銀行が国債を買えば、手元から現金が出ていきます。市場の通貨量は少しずつ細ります。
ここでもイメージを深めてもらうための例を出してみましょう。
日本銀行が「10億円ぶんの国債を売ろう」と決めたとします。その国債を魅力的だと感じた市中銀行Aは、購入のために日銀へ向けて資金を支払います。
取引が成立した瞬間、起きているのは次の二つの動きです。
まず、銀行Aの口座から日銀の口座へ「10億円」が移動し、市場からお金が吸い取られます。紙幣が吸い込まれていくわけではありませんが、数字としての資金が市場から姿を消すのです。
次に、銀行Aはその代わりに国債を受け取ります。すると、銀行の資産は、
現金(すぐ使える資金) → 国債(動きにくい資産)
へと変わります。
手元の現金が減るというのは、銀行にとって「自由に貸し出せる力」が弱まるということです。
お金の量が減ると、融資は慎重になり、ローンの金利も上がりやすくなります。その結果、物価の上昇は落ち着き、景気の過熱も静まります。
物価が上がり続けるときや、「景気が走りすぎている」と判断されるときに、一度立ち止まり、流れを整えるために行われる政策が売りオペレーションです。
ゼロ金利政策、マイナス金利政策とは?
長い不況のトンネルを抜け出そうとする中で、日本は西暦1999年(平成11年)にゼロ金利政策を導入しました。ゼロ金利とは、短期金利をほぼゼロまで引き下げる政策です。
さらに西暦2016年(平成28年)から開始されたマイナス金利政策では、市中銀行が日本銀行に預けている一部の預金に対して、逆に「手数料」がかかるしくみが導入されました。
「預けても利子がつかないどころか、手数料がかかるなら、預けるより誰かに貸したほうがよい」
市中銀行がそう考えるように促し、世の中にお金を回そうとした政策なのです。
アベノミクスの「黒田バズーカ」や「異次元緩和」と呼ばれた一連の政策も、この流れの中にあります。日本銀行は、買いオペレーションを中心に、世の中にお金を循環させるための大胆な一手を打ち続けてきました。
公開市場操作以外の伝統的金融政策 ──預金準備率・公定歩合・そして窓口規制の歴史
金融政策には、私たちが普段意識しない場所で社会のリズムを整える、もうひとつの系列があります。それが「公開市場操作以外の伝統的な政策手段」です。
今日もっとも重要なのは公開市場操作(オペレーション)ですが、そこに至るまでには、銀行の行動を制度で整えるさまざまな仕組みが存在していました。
歴史をたどりながら、現在も使われる手段と、役割を終えた手段を丁寧に見ていきます。
預金準備率とは?
銀行が受け取った預金は、すべて貸し出しに回せるわけではありません。一定割合は、日本銀行に預けておく義務があります。
銀行は日々、預金者の決済や払い戻しに応える必要があります。そのため、預かった預金のすべてを貸し出してしまうわけにはいきません。一定の額を「支払いのための準備金」として日本銀行に預けておくことが預金準備制度の核心です。
だからこそ、決められた割合を必ず日銀に預けておく割合が 預金準備率です。
預金準備率が上がると、銀行は多くの資金を日銀に預けなければならず、貸し出しに回せるお金は減ります。
つまり、
- 預金準備率が上がると、貸出は減少してしまうため、景気を冷ます方向へ向かう
- 預金準備率が下がると、貸出は拡大するため、景気を温める方向へ向かう
という効果が生まれます。
なお、預金準備率については、西暦1991年(平成3年)から預金準備率は変更されていません。
公定歩合とは?
かつて日本銀行は、銀行にお金を貸し出すときの金利を、「公定歩合」 として公表していました。これは「日本の金利のものさし」として、長い間、金融政策の中心に据えられていました。
- 公定歩合が上がれば、銀行の貸出金利が上がることを意味するので、銀行にとってはお金を借りたくなくなる。すると、お金が動きにくくなり、景気が冷える方向に向かう。
- 公定歩合が下がれば、銀行の貸出金利も下がることを意味するので、銀行にとってはお金を借りたくなる。すると、お金が動きやすくなり、景気が温まる方向に向かう。
という連動ルールが機能していたのです。
1970年代から80年代にかけての日本では、金利は市場ではなく行政によってコントロールされていました。
ところが、平成6年(西暦1994年)になると、日本の金利は大きな転換点を迎えます。金利の自由化がほぼ完了し、市場が自分たちで金利を決める時代へと移ったのです。社会の中を流れるお金の量を「上から」コントロールする手法より、市場での取引を通じて細やかに調整する方向へと舵が切られました。
その結果、公定歩合は政策としての力を失っていきます。実質的には使われなくなり、平成18年(西暦2006年)には 「基準割引率および基準貸付利率」 という名称に変更されました。けれども、それは名前を変えたというよりも、役割を終えた制度の“看板替え”に近いものです。
そして現在において、公定歩合操作は事実上、金融政策としては使われていません。教科書に残っているのは、制度の歴史を知るための痕跡としての意味合いが強いのです。
窓口規制(窓口指導)とは?
窓口規制(窓口指導)とは、昭和から平成初期にかけて日本銀行が民間銀行に対して行っていた、「どれくらい貸し出してよいか」を直接伝える運用型の規制のことです。
民間銀行が「もっと企業に貸し出したい」と思っても、日銀が「今年はここまでにしておきましょう」と指示すれば、その線を越えて大きく融資を増やすことはできなかったのです。
なぜそんな仕組みが必要だったのでしょうか。
それは高度経済成長期、日本の経済が前へ前へと走り続けていたからです。企業が設備投資に殺到し、銀行は次々に貸し出します。もしここで融資が歯止めなく膨らめば、バブルのように物価が加熱し、経済が不安定になる危険があったのです。
そこで日銀は、貸し出しの伸び方を見ながら、銀行ごとに「今年の貸出計画」のような指針を出し、必要に応じて融資の勢いを調整していました。これが 窓口規制(窓口指導) です。
しかし時代は変わります。
平成に入ると、金利の自由化が進み、金融はより「市場で決まる」方向へ移行しました。銀行の貸し出し量も、行政指導で抑えるより、公開市場操作や金利政策によって市場全体を通して整える方が適切だという考え方になりました。
その結果、窓口規制(窓口指導)は西暦1991年(平成3年)7月に正式に廃止されました。
金融政策の非対称性──水をかけるのは簡単。火をつけるのは難しい
金融政策には、しばしば 「非対称性」 と呼ばれる性質があります。
つまり、景気の過熱を冷ます(金融引き締め)ときのほうが効果が出やすく、反対に、不景気から抜け出すために景気を温める(金融緩和)ときは効果が出にくいという特徴です。
では、なぜこのような差が生まれるのでしょうか。
「お金を回収する」のは、仕組みとして即効性が高いです。
インフレが進んだとき、日銀は売りオペで市場からお金を回収したりします。市場からお金が減れば、企業は投資を慎重にし、家計もローンを控えるようになります。これは、経済主体が「これ以上お金を使いすぎない」方向に自然と向かうため、政策効果が比較的すぐ現れます。
一方、不景気のときに金利を下げ、市場にお金を大量に供給しても、企業も家計も「借りてまで投資・消費をする気にならない」ことが多くあります。
例えば、今後の先行きが不安で、家計が節約志向にあったり、企業の投資意欲が低下している場合があります。また銀行の融資が慎重なままであることもあります。こういったことが重なると、たとえ資金が豊富でも「動こうとする力」が弱いのです。すると、景気が温まりにくい傾向が出てしまうのです。
また、金利を下げる政策には限界があります。ゼロ金利・マイナス金利まで来ると、それ以上の下げ幅が残っていない ため、追加の効果を出しにくくなります。
これが金融緩和が効きにくい最大の理由です。
【まとめ】金融政策の全体像──社会の“流れ”を整える日本銀行の役割
私たちの社会には、お金が静かに循環する見えない仕組みがあります。電子マネーの支払いも、毎月の給与振込も、すべてはこの流れの延長線上にあります。日本銀行の金融政策は、この流れが速すぎても遅すぎても社会が不安定にならないよう、静かに呼吸を整えるように機能しています。
本稿で見てきたように、金融政策の中心は公開市場操作です。市場からお金を吸い上げたり、反対に送り込んだりして、コールレートを望ましい方向に導きます。これは今日の金融政策の「背骨」であり、もっとも即応性の高い調整手段です。
その一方で、歴史をたどると、預金準備率や公定歩合、さらには窓口規制といった制度も重要な役割を担ってきました。いまでは主役の座を降りた制度もありますが、それらが築いた経験と反省の上に、現代の金融政策が成立していることがわかります。
金融政策を理解するうえで欠かせない視点が、最後に扱った「非対称性」です。景気を冷ます政策は比較的速く効く一方で、温める政策は効果が出にくい。大量のお金を供給しても、人々の心理や将来への不安が強ければ動きが鈍り、景気はなかなか回復しません。金融政策だけでは解決できない局面があるからこそ、財政政策や為替政策との協調──ポリシーミックスが求められてきたわけです。
こうして見てくると、日本銀行の金融政策とは、「お金の量」だけを動かす作業ではないことが分かります。人々の行動、企業の意欲、社会全体の期待、歴史の教訓。そうした幅広い要素を見渡しながら、目に見えない流れに静かに手を添える仕事です。
景気とは、数字の集合ではなく、社会に息づく「リズム」そのものです。そのリズムがゆっくり乱れ始めたときに、そっと整え直す力をもつ──それが金融政策の本質なのだと思います。