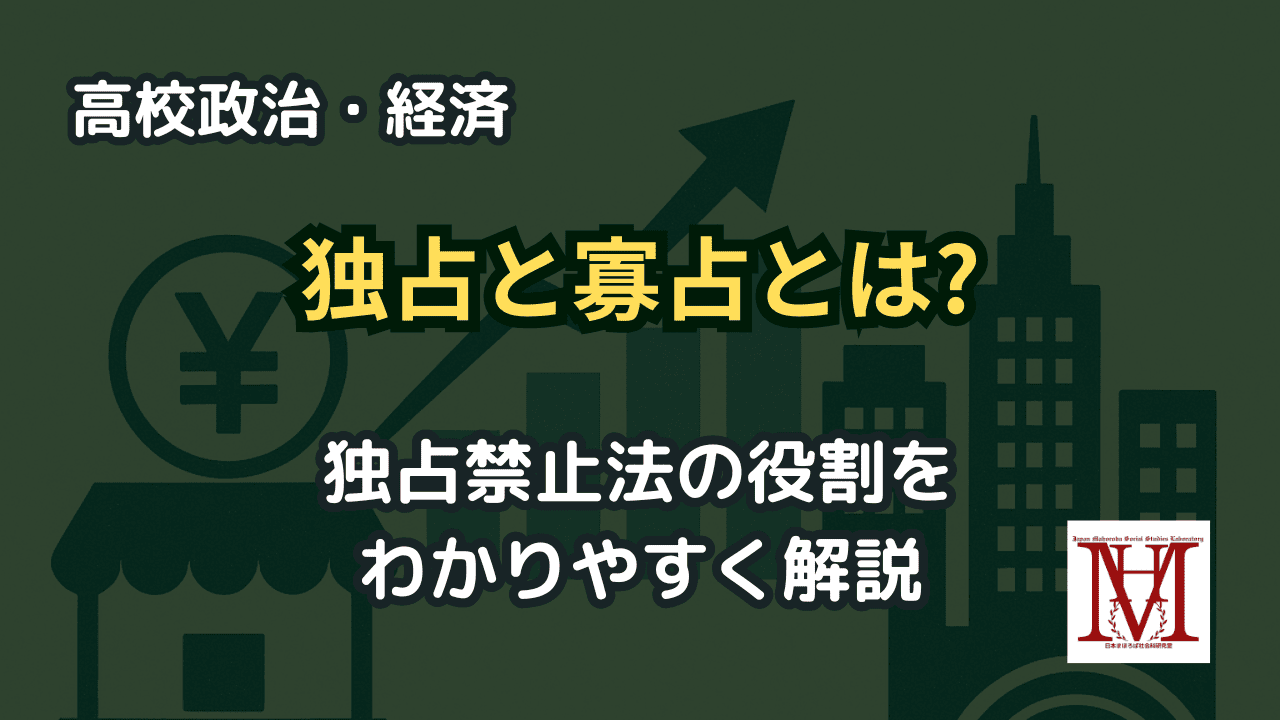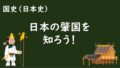みなさんはコンビニやスーパーで、「どのお店でもだいたい同じ値段だな」と感じたことはありませんか? たとえば缶ビールや板チョコ、携帯電話の料金プランなど、会社が違うのに価格は横並び。なぜこんなことが起こるのでしょうか。実はそこには「独占」や「寡占」といった市場の仕組みが関わっています。
独占や寡占の市場では、競争が弱まり、価格が簡単には下がらなくなります。一見すると安定しているように見えますが、消費者にとっては不利なことも多いのです。
今回は、この「独占・寡占」と、それを規制する法律=独占禁止法について見ていきましょう。
「独占」「寡占」とは何か
独占とは?
独占とは、一つの企業が市場全体を支配してしまう状態をいいます。このとき、その企業は「プライスメーカー」、つまり自分で価格を決める存在になります。
例えば、かつてのタバコ産業のように競争相手がほとんど存在しない場合、企業が設定した価格がそのまま市場価格になってしまいます。
電気やガス、水道といったインフラのように、巨額の設備投資が必要な分野では、自然と一社だけが事業を担う「自然独占」が起きやすくなります。
寡占とは?
寡占とは、少数の大企業が市場の大部分を占める状態を指します。
日本のビール業界では、キリン・アサヒ・サッポロ・サントリーの四社がシェアを分け合っていますし、板チョコや牛丼、さらには携帯電話のキャリアも同じような構造です。
こうした市場では、一番力のある企業が「プライスリーダー」となり、その会社がつけた価格に他社も追随します。
その結果、価格が横並びに固定される現象が生まれ、これを「管理価格」と呼びます。
なぜ独占や寡占は起こるのか?
独占や寡占は、ただ企業が欲張ったから生まれるのではありません。
わかりやすい理由としては、いわゆる「規模の利益」と呼ばれるものです。たくさん生産するほど一つあたりのコストが下がり、大きな会社がどんどん有利になるのです。すると、小さな会社は競争に負けて市場から退出し、残った少数の企業がシェアを握ることになります。
電気やガス、水道などのインフラは、もともと巨額の設備投資が必要なので、新しい企業が入りにくく、自然に独占や寡占の形になります。
牛丼チェーンやコンビニも、最初は多くの会社が参入していましたが、長期的には大手数社が残って市場を分け合っているのが現状だと思われます。
独占や寡占はなぜ問題なのか?
独占や寡占が進むと、価格が下がりにくくなり、消費者にとって不利な状況が生まれます。
本来であれば競争によって値段が下がったり品質が向上したりするはずですが、独占や寡占のもとではその力が弱まってしまいます。缶ビールの値段がどの会社でも同じであるように、価格競争がなくなると、企業はテレビCMやパッケージデザイン、ポイントカードのようなサービスでしか差をつけられなくなります。表面上は華やかな比較競争が行われますが、消費者の財布の負担は軽くならないのです。
さらに、大企業が市場を固めてしまうと、新しい会社が入り込む余地が小さくなり、イノベーションが生まれにくくなるという弊害もあります。
市場の自動価格調整機能が働かなくなるので、独占や寡占が起こっている状態は「市場の失敗」と言えます。市場の失敗については、別稿で改めて詳しくお話ししているので、詳しくご覧になりたい方は以下の記事を参照してください。
独占禁止法と公正取引委員会
独立禁止法 [独禁法]とは?
こうした市場の弊害を防ぐために、 西暦1947年(昭和22年)に制定されたのが独占禁止法です。正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます。この法律の目的は、第1条に書かれています。
条文を出してみましょう。太字にしている部分は筆者によるものです。
第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律):e-govより
独占禁止法は、3つの行為を禁止しています。条文から抜き出してみましょう。
1つ目は「私的独占」です。これは、ある企業やグループが競争相手を排除したり支配下に置いたりして、市場を独占的に握ってしまうことを意味します。単に規模が大きいというだけではなく、ライバルを吸収したり取引を制限したりして、競争そのものをなくす行為が問題となります。
2つ目は「不当な取引制限」です。これは、複数の企業が協定を結んで価格や生産量、販売ルートなどを取り決め、競争をやめてしまうことです。カルテルや談合が代表的な例で、本来なら消費者にとって有利に働くはずの競争が抑え込まれてしまいます。
3つ目は「不公正な取引方法」です。これは、取引相手に不利な条件を押し付けたり、ライバルを不当に市場から締め出したりするやり方です。たとえば、仕入れ先に「他の会社には商品を売るな」と強制するような行為がこれに当たります。
こうした行為はいずれも、市場の自由な競争をゆがめ、消費者が不利益を受ける原因となります。そのため独占禁止法はこれらを禁止し、一部の企業に力が集中しすぎないようにすることを目的としています。そして、合併や協定によって生産や販売、価格や技術が不当に縛られることを排除し、企業が自由に活動できる環境を守ろうとしているのです。
そのうえで、この法律の中心にあるのは「公正かつ自由な競争を促進する」という考え方です。競争が守られることで企業は工夫を凝らし、新しい商品や技術を生み出そうとします。その結果、事業が盛んになり、雇用が増え、国民の生活水準も高まっていきます。独占禁止法は、単に企業の行動を縛るための法律ではなく、社会全体を活性化させるための法律なのです。
条文の結びには「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進すること」と記されています。これは、独禁法が一部の大企業のためではなく、国民全体の利益と日本経済の健全な発展を守るためのルールであることを示しています。
公正取引委員会とは?
この法律の運用を担うのが公正取引委員会で、違反があれば排除措置命令や課徴金といった強制力を発動することができます。内閣府の外局に置かれた独立行政委員会で、政府から一定の独立性を保ちながら企業の取引を監視しています。かつては「準司法的機能」と呼ばれる裁判所に近い権限を持ち、自ら審判を行うこともできましたが、西暦2013年(平成25年)以降はその役割が東京地方裁判所に移され、現在は行政機関としての立場が明確になっています。違反があった場合には、排除措置命令や課徴金といった強制力を発動し、公正な競争環境を守る役割を果たしています。
独占や寡占は、市場を一見安定させるように見えて、実際には消費者の利益を損ない、新しい企業の挑戦を妨げます。そのため、自由で公正な競争を守る仕組みとして独占禁止法が存在しているのです。
独占禁止法で禁止されていること
カルテル・談合・ダンピングについて
独占禁止法では、自由な競争をゆがめてしまう行為が禁止されています。
たとえば、複数の企業が話し合って価格や生産量を決める「カルテル」や、公共工事の入札で事前に落札者を決めてしまう「談合」、ライバルを潰すために原価を無視して極端に安く売り続ける「ダンピング」などがそれにあたります。
企業がこうした行為をやろうとするのは、一見するとメリットがありそうに見えるからです。たとえば、「カルテル」で「お互いに値下げはやめよう」と決めれば、激しい価格競争を避けて安定した利益を得られそうに思えます。「談合」も「今回はA社、次はB社」という具合に順番を決めれば、確実に仕事を分け合え、しかも高い価格で受注できるように見えます。ダンピングも、一時的に原価を無視した超安値を続ければ、ライバルを市場から追い出して独り勝ちできるように思えるでしょう。
しかし実際には、これらはいずれも市場の健全な競争を壊してしまいます。カルテルや談合では消費者が本来より高い値段で買わされ、品質の改善も進みません。ダンピングでは、競合が「極端に安い金額に合わせれば赤字」「極端に安い金額に合わせなければ顧客を失う」という苦しい状況に追い込まれ、撤退や縮小に至ります。結果として市場には少数の企業しか残らず、競争が少なくなります。その中で優位に立った企業は、過去の損失を回収するために価格を引き上げても、消費者には他の選択肢が少ないため受け入れざるを得なくなります。
「カルテル」や「談合」や「ダンピング」は、短期的には企業にとって「得策」に見えても、長期的には消費者が高値と選択肢の減少という大きな不利益を被るのです。結果として、消費者は不当に高い値段を払わされ、品質の改善やサービスの向上も期待できなくなるのです。
かつては「合理化カルテル」や「不況カルテル」といって、企業が協力して景気悪化に対応することが認められていた時期もありました。しかし、それでは結局消費者が高い負担を強いられるため、西暦1999年(平成11年)の改正で全面的に禁止されました。
再販売価格維持制度という例外
例外的に「再販売価格維持制度」と呼ばれる仕組みが認められている分野もあります。これは、生産者(出版社やレコード会社など)が小売業者に対して「この商品は必ずこの価格で売ってください」と指定できる制度です。通常であれば、小売店が自由に値段を決めるのが独占禁止法の原則ですが、この場合は値引き販売が禁止され、どの店でも同じ価格になります。まさに「自由競争の例外」として特別に認められているわけです。
「再販売価格維持制度」の対象となるのは、書籍や新聞、雑誌、レコード、音楽テープ、CDの6品目です。本を安売り競争の対象にしてしまうと出版社や書店の経営が立ちゆかなくなり、文化を支える担い手が失われる危険があるためだというのが理由です。そのため、例外的に価格を固定することが認められているのです。消費者にとっても、全国どこでも同じ価格で本が手に入ることには一定の利点があると考えられています。
一方で、電子書籍はこの再販制度の対象外です。そのため、半額セールや期間限定値引きがしばしば行われています。紙の本と違ってネット販売では在庫のリスクや配送コストがなく、仕入れ値の概念も薄いため、割引をしても流通が成り立ちやすいのです。この点は、文化を守るために価格を固定してきた紙の出版物との大きな違いだといえるでしょう。
企業の結びつきについての規制について
独占禁止法が問題視する企業の結びつき
独占禁止法は、企業どうしが結びついて競争を弱めてしまうことを警戒しています。独占禁止法が好ましくないと考える企業の結びつきにはいくつかのタイプがあります。
まず「カルテル」です。先ほども述べましたが改めて説明します。「カルテル」は、同じ産業分野の企業どうしが協定を結び、価格や生産量、販路などをあらかじめ決めてしまう企業連合のことです。たとえば、ジュースを作るA社・B社・C社が「もう値下げ合戦はやめて、500mlペットボトルはすべて150円で売ろう」と裏で話し合えば、それはカルテルになります。見かけ上はそれぞれの会社が独立しているように見えても、実際には競争が止まってしまうため、独占禁止法で禁止されています。
次に「トラスト」は、同じ産業分野の企業が合併・合同して、一つの大企業になる形態です。たとえば、スマホメーカーX社とY社がライバル関係をやめて合併し、新会社「XYモバイル」として市場を支配するようなケースです。カルテルが「協定」で結びつくのに対し、トラストは「一つの会社」にまとまってしまう点が異なります。
最後に「コンツェルン」は、持株会社を頂点として、異業種にわたる企業を子会社や孫会社として系列化し、グループとして支配する企業連携の形態です。たとえば「XYZホールディングス」という会社が、銀行・自動車メーカー・スーパーマーケットを子会社に収め、グループ全体で経済を動かすような状態です。戦前の三井や三菱の財閥グループは、この典型例でした。
これに似た形態として「コングロマリット(複合企業)」があります。こちらは、合併や買収を繰り返し、一つの企業が異業種にまたがって多角化していくスタイルで、アメリカのゼネラル・エレクトリックなどが代表例です。コングロマリット自体はただちに違法ではありませんが、規模が大きくなりすぎて競争を妨げたり、系列内で市場を囲い込んだりすれば、独占禁止法の規制対象となります。
これらの形態はいずれも、規模の拡大や効率化といったメリットを持つ一方で、行きすぎれば競争を奪い、消費者に不利益をもたらす危険性があります。そのため、独占禁止法によって規制や監視の対象とされているのです。
持株会社[ホールディングス]の禁止と解禁
持株会社 [ホールディングス]とは、他の会社の株式を保有し、その会社の経営を支配(グループ統括)することを目的とした会社です。株を単に投資目的で持つのではなく、グループ全体を管理し、経営の方向性をコントロールするための仕組みと言えます。ここからは、持株会社をめぐる歴史的な経緯を見ていきましょう。
戦前:財閥の成長
戦前の日本では、三井・三菱・住友といった財閥が、持株会社を頂点に巨大な企業グループを形成していました。なぜ財閥がこれほどの力を持つようになったのでしょうか。
明治時代、日本は富国強兵策の一環として政府が鉄道・造船・鉱山などの産業を育成しました。その後、これらの官営事業が民間に払い下げられると、三菱財閥の海運業や三井財閥の銀行業などが大きく発展します。さらに、第一次世界大戦中は欧米諸国が戦争に注力していたため、日本の輸出産業が急成長しました。この「大戦景気」で財閥は莫大な利益を上げ、鉱山・造船・銀行・商社など多様な業種の企業を次々と傘下に収めていきました。
財閥は、自前の銀行を通じてグループ企業に資金を融通し、製造業で生産し、商社で販売するという「資金から流通まで一貫した経営」を可能にしました。その結果、日本経済に圧倒的な影響力を持つ存在となり、あまりの強大さに公正な競争を妨げるとの批判を受けるほどでした。
戦後:財閥解体と持株会社の禁止
こうした財閥による経済支配を問題視したGHQ(連合国軍総司令部)は、戦後の占領政策において財閥解体を断行します。
独占禁止法が制定された西暦1947年(昭和22年)当初、特に警戒されたのは財閥でした。
では、なぜGHQが財閥解体を推し進めたのかというと、大きく二つの理由がありました。
- 財閥が戦前の軍需産業を支え、戦争遂行の経済的基盤となっていたこと。
- 少数の財閥が経済を独占していたため、自由で公正な市場経済を築くには解体が必要だったこと。
この政策の一環として制定された独占禁止法では、一つの会社が他社の株式を大量に保有して強い支配力を持つこと(=持株会社の設立や既存の会社の持株会社化)を禁止しました。要するに、戦後の日本では「持株会社」は新しく作ることも、既存の会社形態に変更することも法律で長らく禁じられたのです。これ以来、「持株会社」という言葉は財閥による独占支配の象徴として長い間忌避される存在となりました。
1997年以降:持株会社の復活
しかし、高度経済成長を経てバブル崩壊を迎えた1990年代、日本経済は国際競争の荒波にさらされます。その中で、企業が効率的に経営資源を活用し、生き残るためには新しい体制が必要だと考えられるようになりました。持株会社は、各事業を子会社として分社化し、それぞれに専門性を持たせつつ、グループ全体としてはトップが方向性を統一できます。たとえば、銀行部門と保険部門、流通部門を分けて子会社にすれば、現場の独自性を保ちながら資金や人材を柔軟にやり取りできるのです。
こうしたメリットが見直され、西暦1997年(平成9年)の独占禁止法改正で持株会社の設立が解禁されました。今日では、「セブン&アイ・ホールディングス」や「みずほフィナンシャルグループ」など、多くの大企業がこの形を採用しています。ただし、カルテルや談合のように競争そのものを潰す行為とは異なり、持株会社も「競争を著しく制限しない範囲」でのみ認められており、公正取引委員会の監視の下で運用されているのです。
まとめ
独占や寡占は、企業にとっては安定をもたらすように見えても、消費者にとっては高値や選択肢の減少、イノベーションの停滞といった不利益をもたらします。だからこそ、日本では西暦1947年(昭和22年)に独占禁止法がつくられ、公正取引委員会が監視の役割を担ってきました。
もちろん、企業の結びつきがすべて悪いわけではありません。持株会社のように、経営の効率化や専門性を高める仕組みは条件付きで認められています。大切なのは「競争を守りながら経済の発展につなげる」こと。独占禁止法は、そのバランスを取るためのルールなのです。
私たちが毎日手に取る商品やサービスの価格の裏側には、こうした法律や仕組みがある。そう考えると、「経済のしくみ」はぐっと身近に感じられるのではないでしょうか。