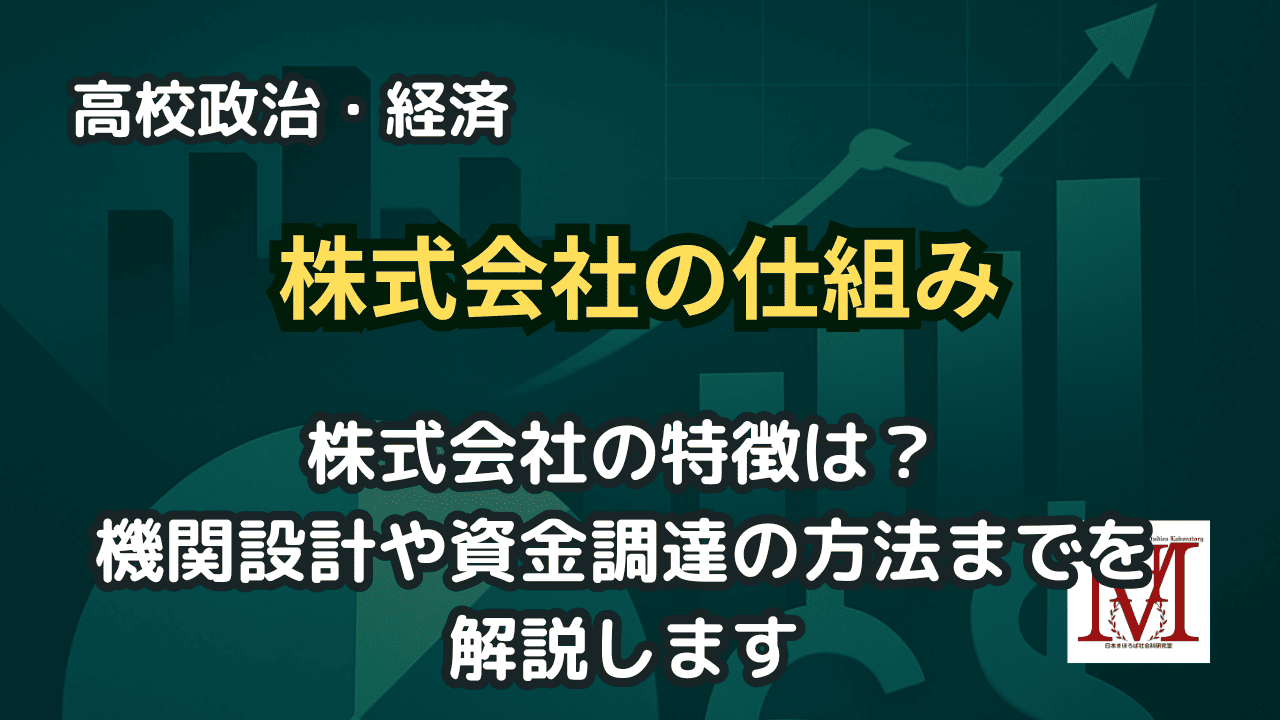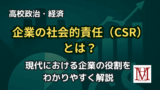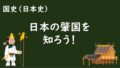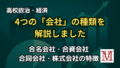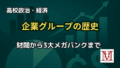もし、皆さんが「夢の車」を作ろうと思ったらどうしますか?
土地を買い、巨大な工場を建て、最先端の機械をそろえる――その費用は数千億円にもなります。とても一人のお金や銀行の融資だけではまかなえません。では、なぜトヨタやホンダのような大企業は実際にそれを可能にしているのでしょうか?
その答えが「株式会社」という仕組みにあります。株式会社とは、社会全体から資金を集められる制度であり、日本や世界の経済を支える大きな柱なのです。
株式会社という会社形態のメリット
株式会社は少額からでも投資できる仕組み
株式会社の最大のメリットは、巨額の資金を多くの人から集められることにあります。たとえば、皆さんが新しい自動車を製造するために工場を建てたいとしましょう。夢の車を作りたいと思っても、土地の購入、巨大な建物の建設、最先端の生産ラインの導入には数千億円もの資金が必要です。さらに、新型車の開発には数百億円規模の研究開発費もかかります。これを一人のお金や銀行の融資だけでまかなうのは不可能です。
そこで株式会社では、資本を小さな単位である株式に分けて販売します。株を買った人は「株主」と呼ばれ、会社の一部を所有する立場になります。株式が細かく分けられているため、1人がいきなり数千万円や数億円を出す必要はなく、数万円や数十万円といった金額から参加できます。つまり、少額からでも大企業の一部を持てるのが魅力です。
株式会社は、少額からでも多くの人が資金を出し合える仕組みを持っています。そのため、個人や法人がリスクを分散しながら大規模な事業に参加でき、会社は安定した資金を得られるのです。株主にとっては配当や売却益、議決権などの利益があり、会社にとっては大きな資金を集めることができる――この「相互利益の仕組み」こそが株式会社の最大の強みといえます。
株主のメリット
株主にはいくつかのメリットがあります。そうでなければ、自分から出資することはないでしょう。会社が利益を上げれば、その一部を配当として受け取ることができますし、株価が上がれば買ったときとの差額で売却益(キャピタルゲイン)を得ることも可能です。
株主には大きく分けて「個人株主」と「法人株主」があります。法人株主はさらに、銀行や保険会社などの金融機関、メーカーや商社などの事業法人、そして海外の投資家である外国法人に分けられます。
日本の特徴としては、株主の大部分を法人が占めている点が挙げられます。近年の統計では、法人株主(金融機関・事業法人・外国法人)を合わせると全体の7割前後になっており、個人株主の割合はアメリカに比べて小さいのです。アメリカでは株を持つ個人投資家が非常に多いのに対し、日本では法人同士が株を持ち合う「持ち合い」が伝統的に多かったためです。
こうした違いから、日本企業は株主の顔ぶれに法人が多く、株主総会もアメリカのように個人投資家が大勢参加する光景とは少し異なるのです。
株主は株式と引き換えに資本金を出資する立場であり、保有する株数に応じて株主総会における議決権の強さが変わるのも特徴です。つまり、多くの株を持っている株主ほど会社の意思決定に与える影響が大きくなります。この点、1人1票持っている選挙権や国会における国会議員の表決権などとは異なります。
また、会社によっては経営陣や従業員に対して「ストックオプション」という制度を設けています。これは、あらかじめ決められた価格で自社株を購入できる権利で、株価が上がれば大きな利益を得られるため、従業員のモチベーション向上にもつながります。
株主は、出資額に応じて利益の分配や議決権を得られる立場です。日本では法人株主が多いという特徴もあります。株式を持つことで会社の一部を所有しつつ、有限責任によってリスクは出資額に限定されるため、安心して投資できる仕組みになっています。
自己株式について
ここで一つ注意したいのが「自社株(自己株式)」です。これは、会社が自分の発行した株を自分自身で持つことを指します。本来、株は会社の「持ち主」である株主が持つものであり、会社自身が株を保有すると役割が混ざってしまいます。そのため、原則として会社は自社株を持つことはできません。もし自由に自分の株を買い取れると、事業に使うべき資金が株主への払い戻しに回り、経営が不安定になる危険があるからです。
ただし、西暦2001年(平成13年)の商法改正以降は、「金庫株」と呼ばれる自社株の保有が認められるようになりました。かつては取得できる目的が限定されていましたが、現在ではその制限はなく、会社の判断で自己株式を取得することができます。
実務では大きく2つの目的で活用されます。ひとつは株主への利益還元です。たとえば、会社が利益の一部で自社株を買い取れば、市場に出回る株が減って1株あたりの価値が高まり、株主にとってメリットになります。もうひとつは企業防衛や従業員のモチベーション向上です。敵対的買収を防ぐために自社株を保有したり、ストックオプションに活用したりします。
このように、株主は配当や議決権といったメリットを享受できるだけでなく、会社の経営の安定や防衛の仕組みにも深く関わっているのです。
有限責任の仕組み
そしてもう一つ大事なのが、株主の責任の範囲です。株主は有限責任しか負いません。有限責任とは、会社が倒産した場合でも株主が失うのは出資した金額に限られるという仕組みです。たとえば100万円分の株を持っていても、会社が大きな借金を抱えて倒産した場合に失うのはその100万円までで、それ以上の借金を個人が背負うことはありません。
この仕組みのおかげで、株主は自分の生活や財産すべてを危険にさらすことなく会社に投資できます。つまり「出資した分だけのリスクで会社の利益に参加できる」ため、多くの人が安心してお金を出し合い、大規模な事業が可能になるのです。
所有と経営の分離
しかも、株主が自動車工場で働いたり経営の細部に口出ししたりする必要もありません。日々の経営は取締役という経営のプロが担います。株主は資金を提供し、取締役は経営を行う。この分業体制のことを、商法学で「所有と経営の分離(separation of ownership and management)」と言います。
「所有と経営の分離」と少額からでも投資できる「株式」という仕組みがあるからこそ、株式会社は安心して大規模な事業資金を社会から集めることができるのです。
公開会社について
公開会社とは?
まず「公開会社」という言葉の意味を押さえておきましょう。公開会社とは、株式を自由に他の人に売ったり買ったりできる会社のことです。これを法律用語では株式譲渡の自由の原則と言います。
では、なぜこの自由が大切なのでしょうか。たとえば自動車メーカーの株を持っている人が、「もう少し別の会社に投資したい」と思ったとします。このとき株を自由に売れるからこそ、別の人がその株を買って会社の株主になれるのです。もし自由に売れなかったら、一度株を買った人はずっと手放せず、新しい人が会社に資金を出すチャンスも失われてしまいます。
ここで「それなら会社が株を買い取ってくれればいいのでは?」という疑問も出てくるかもしれません。しかし、もし株主が株を手放すたびに会社が買い取る仕組みだったらどうなるでしょう。会社のお金は事業に使うためのものであり、株主の都合で次々と払い戻していたら、会社の資金は不安定になってしまいます。これでは安心して事業を進められません。
そこで考え出されたのが、株式を会社ではなく他の人に自由に売れる仕組みです。株主は必要になれば第三者に売ってお金を回収でき、会社は事業に必要な資金をそのまま確保できます。これを投下資本の回収と言います。つまり、株式譲渡の自由は「株主の資金回収の自由」と「会社の資金の安定」を両立させるためにあるのです。
このように株式を自由に売買できる会社を「公開会社」と呼びます。
反対に、株を自由に売れず会社の承認が必要な会社は「株式譲渡制限会社」と呼ばれます。こちらは中小企業や家族経営の会社で多く見られます。くわしくは後述します。
株式譲渡のやり方
公開会社の大きな特徴は「株式を自由に売り買いできること」ですが、実際に株を譲渡するときには、かつては「株券」という紙の証書がやり取りされていました。株券には会社名や株主名、株数が書かれており、それを相手に渡すことで「株主としての地位」も移転する仕組みになっていたのです。
しかし、この株券方式には紛失や偽造のリスクがあり、大企業のように株主数が膨大になると管理が煩雑になりました。そこで、西暦2009年(平成21年)から、法律上は株券を発行しないのが原則とされ、現在は証券会社の口座で株主の権利が電子的に管理されるようになっています。もっとも、定款で定めれば「株券発行会社」として株券を発行することは可能です。ただしこれは例外的な制度であり、現在の株式市場ではほとんど利用されていません。
では、今は株の売買はどのように行われているのでしょうか。
現在では、株を売りたい人と買いたい人が証券会社を通じて注文を出し、証券取引所(たとえば東京証券取引所)のコンピュータシステムで自動的にマッチングされます。そして売買が成立すると、株主名簿に新しい株主が登録され、電子的に株式が移転します。
要するに、株券を直接やり取りする代わりに、証券会社と取引所のシステムを通して株主が入れ替わるという仕組みになっているのです。これにより売買がスピーディーかつ安全に行えるようになりました。
公開会社の機関
社会から大規模な資金を集める公開会社では、「誰が決定し、誰が監視するのか」という仕組みを明確にしておく必要があります。これを会社の機関と呼びます。
最高意思決定機関は株主総会です。株主総会は国でいえば「国会」にあたるもので、株主が集まって会社の重要な方向性を決定します。また、会社の発行済株式(=会社が世の中に出している全ての株式)の1%以上を持っている少数株主も株主総会で議題を提案することができます。ここでは、取締役や監査役を選んだり逆に解任できたり、合併や新しい工場建設といった重大な計画を承認したりします。たとえば自動車メーカーが「次の工場を日本に建てるのか、それとも海外に建てるのか」という大きな議題を検討する場合、それは株主総会で決議されるのです。株主は「一株一票」の権利を持ち、保有株数が多ければ多いほど影響力が大きくなります。
株主総会で選ばれるのが取締役であり、彼らが集まって構成する取締役会は「内閣」のような存在です。公開会社では取締役会の設置が必須であり、少なくとも3人以上の取締役が必要とされています。「会議体」なので、多数決で決められる最低人数が必要だということで3名だとされています。取締役会は実際の業務執行の決定を行う機関で、たとえば「電気自動車の研究開発に三千億円を投資するか」「新しいSUVを欧州市場に投入するか」といった具体的な戦略を決定します。会社の日常的な意思決定は、この取締役会を中心に行われるのです。そして取締役会で対外的取引の代表者として代表取締役が選ばれます。
さらに公開会社では、監査役の設置も義務づけられています。監査役は、取締役の経営が正しく行われているかを監視する役割を担います。もし監査が機能しなければ、不正会計やリコール隠しといった問題が発生し、株価が急落して株主に大きな損害を与えます。実際に世界の自動車業界でも、監査体制の甘さが原因で不正が発覚し、社会的信用を失った事例がありました。だからこそ公開会社では、取締役会と監査役の二本柱を必ず整えて、経営が健全に行われる仕組みを持っているのです。
これに加え、大規模な(資本金5億円以上、負債総額200億円以上の公開会社)公開会社では、これに加えて会計監査人の設置も必須です。会計監査人は公認会計士や監査法人であり、専門的な立場から会社の財務諸表(決算書)をチェックします。たとえば自動車メーカーのように数兆円規模の売上や投資を扱う会社では、素人目では分からない会計処理の妥当性を専門家が検証するのです。
そもそも財務諸表とは、企業の経営状態を数字で表す基本的な書類のことです。代表的なものに、
「会社がどれだけお金を稼ぎ、どれだけ使ったか」をまとめた損益計算書(P/L)、「会社が今どんな財産を持ち、どれくらい借金をしているか」を表すバランスシート(B/S:貸借対照表)、そして
「会社のお金が入ってくる流れと、出ていく流れ」を示すキャッシュフロー計算書があります。企業はこれらを会計基準に従って作成し、1年間や半年、四半期ごとにまとめて決算書として公表します。投資家や株主はこの決算書を見て「この会社は利益を出しているのか」「借金は返せそうか」と判断するのです。もし財務諸表の内容が悪ければ「この会社は危ないかもしれない」と不安が広がり、株価が急落することもあります。だからこそ、特に大きな会社では、専門家による会計監査人のチェックが欠かせないのです。
しかし、それでも不正が行われることがあります。たとえば、実際より利益が大きいように見せかける粉飾決算です。粉飾決算が発覚すれば、会社の信用は失われ、株主や投資家に大きな損害を与えます。このような事態を防ぐために、公開会社にはディスクロージャー(情報開示)の徹底と、経営者が株主や社会に対して説明責任(アカウンタビリティ)を果たすことが求められています(「ディスクロージャー」や「アカウンタビリティ」については別稿を参照。会社の社会的責任[CSR]について合わせて述べています)。
株主が会社の役員に対して責任を追及できる仕組みとして株主代表訴訟があります。これは、会社の取締役などが不正をしたり会社に損害を与えたりした場合に、一定の要件を満たした株主が会社に対して裁判を起こす制度です。会社の経営陣(例えば取締役や監査役などの会社の役員を指す)に対して損害賠償を起こすことができます。株主が直接「会社の利益を守るために」行動できる仕組みであり、経営者に対する強いけん制の役割を持っています。
このように、株主総会(国会=立法)、取締役会(内閣=行政)、監査役(裁判所に相当するチェック機能=司法)、そして大規模な会社では会計監査人という役割分担があるからこそ、公開会社は安心して多くの人から資金を調達できる仕組みになっているのです。
その他の機関設計の方法 – 指名委員会等設置会社と監査等委員設置会社
上のような機関設計が会社法の基本でしたが、企業の不祥事も多くあり、ステークホルダー(企業活動によって影響を受けたり、影響を与えたりする「利害関係者」全般を指す言葉)に大きな影響を与えることにもなりました。
そこで、新しいコーポレート・ガバナンス[企業統治]の方法が模索されるようになりました。その結果導入されたのが以下の2種類の機関設計の方法です。
なお、公開会社の章で紹介していますが、法的には後述する「株式譲渡制限会社」でも導入することはできます。しかし、株主が少なく経営もシンプルなことが多い「株式譲渡制限会社」で、この複雑な制度を導入する必要はほとんどなく、実務的には上場企業など株主が多い大規模な公開会社が中心であるため、この章で取り上げることにしたいと思います。
指名委員会等設置会社 ― アメリカ型ガバナンスの導入
まず登場したのが指名委員会等設置会社です。これは西暦2002年(平成14年)の商法改正で導入されました(西暦2003年(平成15年)に施行。当時は「委員会設置会社」と呼ばれていました)。
背景には「国際的に通用するガバナンス(企業統治)の仕組みを整えたい」という狙いがありました。特にアメリカ企業では取締役会の権限を細かく分けて透明性を高めており、日本でも同様の仕組みを採り入れる必要があると考えられたのです。
この会社形態では、取締役会の下に必ず3つの委員会を置きます。
- 指名委員会:社長や役員を誰にするか決める
- 報酬委員会:役員の給料・報酬を決める
- 監査委員会:会計や業務を監査する
これらの委員会はいずれも過半数が社外取締役で構成される点です。つまり、外部の人が必ず経営の監督に加わり、内部の人間だけで意思決定をするのを防ぐ仕組みになっています。これによって、取締役会が人事や報酬を恣意的に決めることを防ぎ、透明で公正な企業運営を実現しようとしました。
取締役会は大きな方針を決める役割に専念し、日々の業務執行は執行役が担います。ここでも監査役は置かれず、監査委員会がその役割を担います。
もちろん、大規模会社であることが多いため、会計監査人の設置は必須です。つまり、社内の「監査委員会」と社外の「会計監査人」の二重のチェックで、株主や投資家の信頼を確保する仕組みです。
監査等委員会設置会社 ― 日本型の折衷案
しかし、指名委員会等設置会社は仕組みが複雑で、人材やコストの負担も大きいため、なかなか普及しませんでした。日本では社外取締役の確保が難しく、人事や報酬の決定権を外部に大きく委ねることへの抵抗感も強かったため、この制度を採用した会社は限られました。導入から10年以上たっても、実際に移行した企業はわずか数十社にとどまったのです。
そこで西暦2015年(平成27年)の会社法改正で導入されたのが、監査等委員会設置会社です。
こちらは日本型の折衷案といえます。監査役を置かず、取締役会の中に「監査等委員会」を設置する方式で、監査機能を強化します。この委員会には社外取締役が必ず過半数入ることが義務づけられており、経営の内部に外部の目を組み込むことがポイントです。
「取締役会中心の運営は維持しつつ、社外取締役の力を強めて透明性を高める」―これが監査等委員会設置会社の狙いです。やや柔軟で導入しやすいため、日本企業でも一定の普及が見られます。
こちらも大規模な会社であれば会計監査人の設置が必須です。つまり、「監査役は置かない」「取締役会の中で社外取締役が監査を担う」「会社の規模が大きい場合には、会計は会計監査人が外部から専門的にチェックする」という特徴を持っています。
近年の役職名の変化(CEO・COO・執行役員)
現代の企業の特色の一つに、経営層の役職名の変化があります。従来の日本企業では「社長」「専務」「常務」といった日本語の肩書きが一般的でした。しかし近年では、CEO(最高経営責任者)やCOO(最高執行責任者)といった英語由来の肩書きを用いる企業が増えています。
背景には企業活動のグローバル化があります。海外の投資家や取引先にとって、「社長」「専務」など日本独自の呼称ではその役割が分かりにくいことがあります。そこで、国際的に通用する役職名を採用することで、経営体制を外部にも分かりやすく示し、透明性を高めようとしているのです。
例えば、CEOは Chief Executive Officer の略で会社全体の経営戦略を最終決定するトップ、COOは Chief Operating Officer の略で策定された戦略を実行に移す責任者です。さらにCFO(最高財務責任者)は Chief Financial Officer、CTO(最高技術責任者)は Chief Technology Officer の略で、このように分野ごとに専門の責任者(総称して「CxO」)を置く企業も増えています。これによって経営の役割分担が明確になり、意思決定が効率化するとともに、グローバルな競争環境にも対応しやすくなります。
ここで重要なのは、これらの役職名は日本の会社法に明確な規定がないという点です。会社法が定めているのは「取締役」「代表取締役」「監査役」といった法律上の地位であり、CEO・COO・CFOといった肩書きは、企業が独自に定めて運用している呼称にすぎません。つまり、呼び名は英語であっても、法律上の権限は「代表取締役」などの法的地位が担う構造は変わらないのです。
一方、日本発の役職名として近年普及しているものに執行役員があります。執行役員とは、取締役会(会社の経営方針を決定する会議)が決めた方針に従って実際に業務を執行する権限を持つ役職者のことです。法律上の明確な定義はありませんが、一般には取締役より下位のポジションで、現場での経営判断を迅速に行う役割を担います。ソニーなど多くの大企業が導入しており、経営スピードの向上に寄与しています。
役職名の変化が現代の特色とされるのは、企業が「国際化」と「経営の効率化」という二つの課題に同時に取り組んでいる表れだからです。海外に対しては英語の役職名を使って透明性を示し、国内においては執行役員制度で迅速な経営判断を可能にする。肩書きひとつにも、グローバル化への対応と変革への意志が色濃く反映されているのです。
株式譲渡制限のある株式会社について
先ほども概観したように、株式会社は本来、株式を自由に売り買いできる「株式の譲渡自由の原則」に立っています。なぜなら、その方が多くの人が投資に参加でき、会社が資金を集めやすいからです。
しかし、すべての会社が全国から資金を集めたいわけではありません。たとえば家族で経営する会社や、信頼できる仲間で立ち上げた会社では、知らない人が突然株を買って株主として入り込むと経営が混乱する恐れがあります。
こうしたケースに対応するために、会社法では株式譲渡制限会社という仕組みを認めています。株を他人に売るときに会社の承認を必要とすることで、株主を信頼できる範囲に限定できるのです。これによって、少人数で安定的に経営したい会社は、外部の人に左右されずに会社を続けられます。特に中小企業や同族会社では、この制限が経営の安定に直結します。
一方で、なぜ「株式の譲渡自由の原則」が株式会社の基本であるにもかかわらず、このような制限が法律で許されているのでしょうか。
理由は、株式会社の形が大企業だけでなく中小企業にも利用できるようにするためです。もし株式譲渡の自由しか認められなければ、中小企業は望まない外部の株主に介入されるリスクを抱えることになり、株式会社という制度を選びにくくなってしまいます。
そこで会社法は、原則としては譲渡自由を保ちながらも、例外的に「譲渡制限」を設けられるようにして、株式会社という制度を幅広い会社が使えるように設計しているのです。
株式譲渡制限株式会社の機関
株式譲渡制限会社のもう一つの特徴は、機関設計をシンプルにできることです。公開会社では取締役会や監査役、場合によっては会計監査人まで設置する必要がありますが、譲渡制限会社では必ずしもそうではありません。取締役が一人だけでも会社を運営することができ、監査役の設置も必須ではありません。
そのため、中小企業では「社長=唯一の取締役」といった形も可能であり、現実的に経営の実態に合わせやすい柔軟な制度となっています。
株式会社の資金調達の方法
ここから自己資本と他人資本の解説をしたいと思いますが、企業の資金調達の方法については、別稿で詳しく解説しているので、気になるみなさんはぜひ参考にご覧ください。
自己資本とは何か
会社が事業を進めるためには、まずお金が必要です。その調達方法の一つが自己資本です。自己資本には大きく二つの形があります。
一つは内部留保です。これは会社が事業で得た利益を配当せずに社内に残しておくものです。たとえば自動車メーカーが前年の利益から一部を新型車の研究開発費に回す、これが内部留保です。
もう一つが株式の発行です。会社は資本を株式という小さな単位に分け、それを投資家に売ることで資金を集めます。株を買った人は株主となり、会社の一部を所有する立場になります。株主は会社が利益を出せば配当を受けられますし、株価が上がれば売却益[キャピタルゲイン]を得ることもできます。この仕組みがあるからこそ、公開会社は巨額の資金を社会全体から集められるのです。
他人資本とは何か
もう一つの資金調達の方法が他人資本です。これは簡単にいえば「借金」であり、返済義務があります。代表的なのは銀行からの借入と、社債の発行です。
銀行借入は、会社が金融機関からお金を借りて利子をつけて返すものです。社債は、会社が投資家に対して「一定期間後に元本と利子を返す」と約束して資金を集める方法です。どちらも返済義務があるため、株式の発行とは大きく異なります。
資金調達における公開会社と譲渡制限会社の違い
公開会社は、株式を自由に売買できるため、多数の投資家から株式発行によって巨額の自己資本を調達できます。たとえば自動車メーカーが新しい工場を建設するとき、株式を追加発行して社会全体から数千億円単位の資金を集めることが可能です。
一方で、株式譲渡制限会社は株主を限定しているため、大規模な株式発行による資金調達には向いていません。その代わりに、銀行からの借入や社債発行といった他人資本に依存する割合が比較的高くなります。
特例有限会社とは?
有限会社という制度の歴史
かつて日本には、株式会社とは別に有限会社という会社形態が存在しました。
有限会社は、西暦1938年(昭和13年)の有限会社法で創設され、中小企業向けに設けられた制度です。当時の最低資本金は5万円で、株式会社(最低資本金10万円)に比べてハードルが低く、中小企業でも法人格を持てるようにしたものでした。
その後、制度改正を経て、有限会社の最低資本金は300万円に引き上げられました。一方、株式会社は最低資本金が1000万円とされ、両者の違いは「大規模か中小規模か」という線引きにありました。
- 有限会社:資本金300万円以上、取締役1名から設立可能、監査役不要
- 株式会社:資本金1000万円以上、取締役3名+監査役1名が必要
このように有限会社は、中小企業が利用しやすいようにデザインされた会社制度だったのです。実際、地域の商店や町工場、家族経営の企業などが有限会社として多く設立されました。
会社法改正による廃止と特例有限会社
ところが、西暦2006年(平成18年)の会社法施行により、状況は大きく変わります。株式会社の設立要件が大幅に緩和され、資本金は1円から、取締役も1名から設立可能となったのです。こうなると、わざわざ有限会社を区別して残す理由はなくなりました。
また、会社制度が二重に存在すると法律や実務の運用が複雑になるため、会社形態を一本化した方が合理的だと判断されました。結果として、新しく有限会社を設立することはできなくなり、株式会社に統一されたのです。
ただし、当時すでに存在していた数多くの有限会社をすべて強制的に株式会社へ移行させると、大きな混乱が生じます。そこで設けられたのが特例有限会社です。既存の有限会社はそのまま存続を認められ、名前も「有限会社」のまま使える一方で、法律上は株式会社の一種として扱われています。余談ですが、そういうことから「有限会社」という名前のつく会社は、少なくとも平成17年以前に設立された会社であるということができるので、長く続いている中小企業だと言えます。
特例有限会社は株式譲渡制限会社に近い性格を持ち、株の譲渡には会社の承認が必要です。また、取締役が1人でも経営できる点や監査役の設置が不要な点など、中小企業向けのシンプルな仕組みが維持されています。
特定有限会社についてのまとめ
特例有限会社は、新しく設立することはできませんが、今も日本各地に存在しています。制度としては株式会社に一本化されつつも、歴史的に有限会社を選んでいた中小企業に配慮して存続が認められているのです。
まとめ
株式会社という制度は、「少額からでも投資できる仕組み」と「所有と経営の分離」の原則によって、多くの人から安心して巨額の資金を集められるように設計されています。株主は配当や売却益、議決権といったメリットを得られますが、その責任は出資額に限定される有限責任です。一方で、会社側は株式譲渡の自由を通じて資金調達の幅を広げ、公開会社や株式譲渡制限会社といった形を取りながら、多様な経営ニーズに対応しています。
また、公開会社では株主総会・取締役会・監査役・会計監査人といった機関が役割を分担し、大規模な事業でも信頼性を保てるように仕組み化されています。さらに国際的な要請や不祥事対応を背景に、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社といった新しいガバナンスの制度も導入されました。
そして、中小企業向けには株式譲渡制限会社や特例有限会社といったシンプルな制度が整備され、どの規模の会社でも株式会社の仕組みを活かせるようになっています。
要するに株式会社は、日本経済の根幹を支える制度として、資金調達・経営監督・企業防衛の三つをバランスよく実現する器なのです。