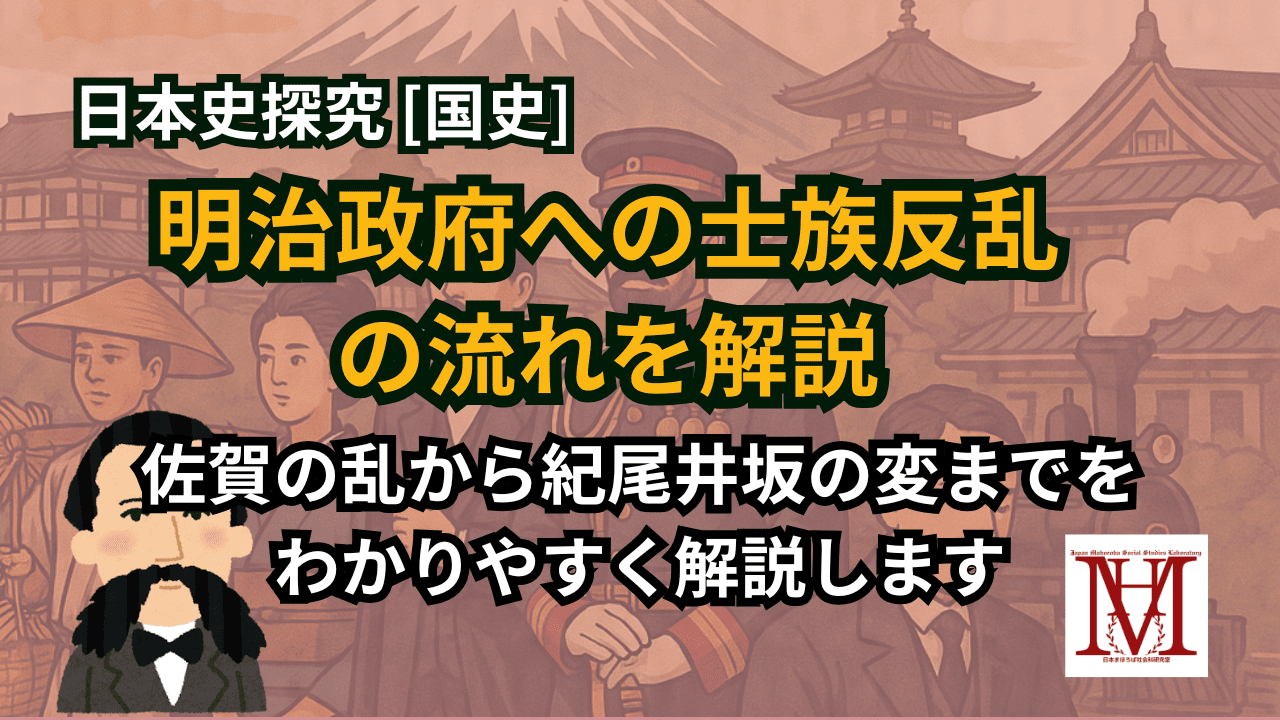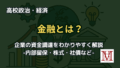明治という新しい時代の幕が開いたとき、日本の人々は期待と同じくらいの不安を抱えていました。武士は刀を失い、農民は暮らしの形を変えられ、誰もが「これから自分たちはどう生きるのか」と問い始めます。
近代国家をつくろうとする明治政府は、徴兵令・廃刀令・秩禄処分など、次々と大胆な改革を打ち出しました。たしかにそれは欧米列強に肩を並べるために必要な制度づくりでした。しかし同時に、それらの政策は長く続いた身分秩序や生活の基盤を揺さぶり、多くの人の誇り・暮らし・信念を深く傷つけることにもなります。
やがて人々の胸に積もった不満や葛藤は、士族による反乱として火を噴き、そして刀ではなく言葉で社会を変えようとする自由民権運動へと流れていきます。
――なぜ人々は立ち上がったのか。
――何を守ろうとし、何に抗ったのか。
――そして、その戦いはどこへ向かったのか。
本稿では、士族の反抗の背景になったことを解説し、佐賀の乱・神風連の乱・西南戦争(西南の役)などの士族反乱をはじめ、さらにその後に始まる言論の時代への転換までをたどりながら、明治国家形成の光と影を見つめていきます。
明治新政府への反抗 – その背景となったこと
徴兵令・廃刀令・秩禄処分
西暦1868年(明治元年)から始まった明治維新は、まさに日本が近代国家への第一歩を踏み出した転換点でした。明治政府は近代国家への道を歩むために江戸時代までの身分制度を大きく変える改革を次々と打ち出しました。そのなかでも、武士の誇りと生活を根底から揺るがせたと考えられるのが、徴兵令・廃刀令・秩禄処分の3つの法令です。
まずは西暦1873年(明治6年)に発布された徴兵令です。この法律は、「国を守るのは武士ではなく、すべての国民だ」という国民皆兵の考え方に基づいてつくられました。満20歳となった男子から毎年抽選で兵士を選抜し、3年間の現役兵役(常備軍)に服させ、その後4年間は予備役に編入するという内容です 。家督を継ぐ者や代人料(身代わり料)を納めた者などには兵役免除規定があり、多くの者が養子縁組で徴兵を逃れようとする社会現象まで生じました。しかし、長く「戦うこと」を自分たちの務めとしてきた士族にとっては衝撃でした。「国を守るのが武士でなくなる」という現実は、彼らの誇りや存在理由を根底から問い直すものでした。
続いて、西暦1876年(明治9年)に出された廃刀令です。これは、警察官や軍人を除いて、人々が刀を差すことを禁じた法律です。この結果、日常で帯刀できるのは皇族や政府高官、軍人・警官など一部に限られるようになりました 。豊臣秀吉の刀狩以来、帯刀は武士のみの特権で「武士の魂」とまで称されていただけに、刀を差すことを禁じられた士族たちは深い喪失感を味わいます 。この年には他にも散髪の奨励など武士の風俗を改める政策が相次ぎ、伝統的武士階級の精神的な支えが次々と取り払われていきました。廃刀令は財政緊縮策の一環でもありましたが、古い武士道精神に生きてきた士族には魂を抜かれるような痛みをもたらしました。
さらに同じ年、秩禄処分が行われました。政府は武士階級に対する最後の経済的優遇策を断ち切ります。江戸時代以来、武士には家禄(給料)が支給され、明治維新後も維新功労者への賞典禄と合わせ「秩禄」として支払われていました。明治政府は西暦1876年(明治9年)にこの秩禄を全廃し、代わりに「金禄公債証書」という有期限の国債を一度だけ交付する制度(秩禄処分)を実施します 。金禄公債の額面は5~14年分の秩禄に相当する金額と定められました 。これにより武士たちは恒常的な俸禄を失い、かつての特権は完全に解体されました。「刀を置き、畑を耕す」――武士たちはなれない商売や農業に活路を求めざるを得なくなります。当時の記録によれば、事業を起こした士族の8~9割が失敗し、家族で食いつめて犯罪に走る者、古道具を売り払い流浪する者も出たといいます 。政府の狙いが財政負担の軽減と近代国家の持続可能性確保にあったとはいえ、「魂」と「生活」の両方を奪われた士族たちにとって、この改革は極めて苛酷なものでした。
こうした改革の背景には、「新しい国家を財政的に持続可能な形にする」という目的がありましたが、当時の士族にとっては、まさに“魂”と“生活”の両方を奪われるような苦しみだったのです。
征韓論の敗北と士族の孤立
加えて、明治初期の政治をめぐる対立が、士族の不満に拍車をかけました。
西郷隆盛や江藤新平らが唱えた征韓論(朝鮮出兵論)は、西暦1873年(明治6年)に政府内の意見対立の末、退けられます。この「征韓論の敗北」は、西郷隆盛や江藤新平を慕う多くの士族たちにとって、理想を打ち砕かれた瞬間でした。彼らは、国家のために働きたいという誇りを持ちながらも、政治の舞台から排除され、生活の手段を失っていたのです。
明治という新しい時代が進むほどに、旧士族たちの居場所は狭まり、彼らの胸には「この国の行く末を自分たちはどう見届けるのか」という葛藤が生まれていきます。
不平士族による反乱
やがてこの不満が、各地の士族反乱へと火をつけていきます。
1874年 佐賀の乱 ― 江藤新平の理想と悲劇
最初の大きな反乱が起きたのは、西暦1874年(明治7年)の佐賀の乱でした。中心人物は、元参議で司法卿(現在の法務大臣にあたる役職)も務めた江藤新平です。
江藤新平は、西暦1873年(明治6年)の征韓論をめぐる政変で下野したあと、板垣退助らとともに日本初の政社である愛国公党を結成して「民撰議院設立建白書」を支持するなど、言論活動の道に進もうとしました。しかし、現実の政治に絶望し、再び故郷・佐賀へ戻ります。そこでは不平士族たちのリーダーとして、西暦1874年(明治7年)に政府に反旗を翻しました。
江藤新平が率いる反乱軍は結局政府軍に敗北しました。江藤新平自身も敗走します。江藤新平は逃亡を図りましたが、皮肉にも彼自身が司法卿在任中に制度化した「指名手配写真」制度によって行方を追われ 、高知県で逮捕されました。江藤新平ら首謀者は処刑され、この乱は失敗に終わります。
江藤新平は司法制度整備など近代国家の礎を築こうと尽力した人物でしたが、最後は自ら築いた法制度の下で裁かれるという悲劇的な結末を迎えました 。
1876年 神風連の乱・秋月の乱・萩の乱 ― 連鎖する士族の怒り
神風連の乱 ― 「忠義」の名のもとに
西暦1876年(明治9年)、熊本で最初に火を吹いたのが神風連の乱でした。
旧熊本藩士の太田黒伴雄を中心とする一団である神風連(敬神党)は、明治政府の近代化政策に強く反発していました。彼らは、かつての攘夷の理想と「天皇への忠義」を純粋に信じる集団であり、廃刀令によって武士の魂を奪われたと感じていたのです。そこで、彼らは「世の乱れを正す」という名目で決起を決意します。
西暦1876年10月、彼らはついに熊本鎮台(近代陸軍の拠点)を襲撃します。しかし、銃と大砲を備えた政府軍の近代的な兵力の前に、刀一本で挑んだ彼らの戦いはわずか一日で鎮圧されました。
その潔さと悲壮さは、武士の時代が終わったことを象徴する出来事として語り継がれています。
神風連の志士たちは、決して乱暴な暴徒ではありませんでした。彼らの行動は、目まぐるしく変わる時代の中で「何を守るべきか」を見失いたくないという、一種の信仰にも似た忠誠心の表れだったのです。
秋月の乱 ― 小藩に生まれた誇りと憤り
同じ明治9年、神風連の蜂起から間もなくして、福岡県の秋月で秋月の乱が起こります。
中心人物は旧秋月藩士の宮崎車之助でした。
秋月藩は小藩ながら尊王攘夷の気風が強く、幕末には西郷隆盛や大久保利通ら薩摩の志士とも交わりを持っていた地域です。彼らは「新政府の政治は天皇の御心に反している」として挙兵しました。
しかし、熊本での神風連の敗北の知らせがすぐに届き、秋月の士族たちも孤立無援のまま戦うことを余儀なくされます。激しい抵抗の末、わずか数日で鎮圧され、多くが捕らえられ処刑されました。
秋月の乱は、地方の小さな藩の人々が、政治の中心から取り残されながらも「正義」を信じて立ち上がった最後の戦いともいえます。それは、力ではなく「志」をもって国を思う士族たちの小さな誇りの証でした。
萩の乱 ― 理想に殉じた前原一誠
そして、同じ年の冬、山口県萩で起きたのが萩の乱です。
指導者は長州藩出身の前原一誠。彼はかつて明治政府の参議も務め、吉田松陰の教えを受けた人物でした。伊藤博文や井上馨、木戸孝允らと肩を並べるほどの政治家でしたが、やがて政府の方針に失望し、「官を辞して民に下る」として政界を去ります。
萩の乱は、単なる地方反乱ではなく、政府中枢にいた人物が理想のために剣を取ったという点で、特異な意味を持ちます。前原一誠は、かつて自ら支えた明治政府が、武士の道を軽んじ、権力に溺れていくことに耐えられなかったのです。前原一誠は同志とともに萩で挙兵しましたが、これも数日で鎮圧され、前原は処刑されました。
前原一誠は最後まで、「誠」の文字どおり、自らの信念に殉じた人物でした。彼の死は、かつての長州の志士たちが掲げた理想――“尊王と民のための政治”――が、新しい国家の現実の中で忘れられつつあることを示す象徴でもありました。
小括
これら三つの反乱は、いずれも小規模で、結果としてすべて鎮圧されました。
けれども、それぞれに共通していたのは、「武士としての誇り」と「国家への忠誠」のはざまで揺れる士族たちの苦悩です。
彼らの抵抗は、明治という新しい時代において「日本人としてどう生きるか」を問い続けた、誠実な叫びでもありました。
1877年 西南戦争 ― 西郷隆盛、最後の戦い
西暦1877年(明治10年)、日本史上最大の内戦であり、士族の反乱の頂点となったのが西南戦争です。政府の記録では「戦争」とされましたが、当時の人々の記憶の中では「西南の役」として語り継がれました。
この戦いの指導者は、かつて「維新の英雄」と称えられた西郷隆盛でした。
西郷隆盛は、西暦1873年(明治6年)、征韓論をめぐって政府の主導権争いに敗れ、政府を辞めて鹿児島へ帰ります。
その後、鹿児島では将来の一大事に備えて集まる場所がほしい、あるいは将来のために学校を設けて教育をしたいという要望があり、それを受けて西郷隆盛は私学校を設立します。西郷隆盛自身は戦いや権力の座を望んでいませんでした。しかし、廃刀令・秩禄処分・徴兵制などの改革によって生活の基盤を失った士族たちは、西郷隆盛を頼って集まってきます。
明治新政府は鹿児島の私学校の勢力を警戒し、西暦1877年(明治10年)1月、弾薬庫から武器や弾薬を密かに搬出します。これに対し、一部の私学校生徒が激昂し、弾薬庫を襲撃して武器を奪う事件が起こりました。この時点でも、西郷隆盛はなお「武力で政府に挑むべきではない」と考えていたとされています。しかし、すでに士族たちの間には
「西郷どんが必ず自分たちを導いてくれる」
という期待と信頼が高まっており、それを退けることは、彼にとって“義を失うこと”と同じ重みを持っていました。
西郷は進んで戦ったのではなく、むしろ、国家への忠誠と仲間への情、その両者の板挟みの末に、責任を引き受けざるを得なくなったのです。その覚悟は、攻撃よりも「自らの身をもって、政府の在り方を問いただす=諫死」に近いものだったとも言われます。
こうして、西暦1877年(明治10年)2月、西南戦争(西南の役)が始まります。
西郷隆盛率いる反乱軍はおよそ4万人。対する政府軍は新しい徴兵制で編成された近代軍でした。
戦いの舞台は九州の中心・熊本。この地には、明治政府が設けた九州防衛の拠点――熊本鎮台がありました。熊本鎮台は、旧熊本城内に設置された陸軍の常設部隊で九州を管轄する軍事拠点になりました。その熊本鎮台を守っていたのが土佐出身の軍人、谷干城です。谷干城は鎮台の兵を率い、熊本城を拠点として籠城戦に挑みました。熊本城は江戸時代の初めに加藤清正が築いた堅城として名高く、「難攻不落」と称えられるほどの防備を誇っていました。谷干城と鎮台の兵たちは、その堅固な城を活かしながら西郷軍の猛攻を退け、ついに城を守り抜いたのです。
戦いはやがて熊本から北上し、田原坂での激戦へと移ります。政府軍は近代的な銃火器と物資補給体制で優位に立ち、士族中心の西郷軍は次第に追い詰められていきました。刀を手に突撃する彼らの姿は、まさに“旧時代の最後の光”のようでもありました。
この戦いで、多くの人々が時代の転換を実感します。
もはや「勇気」や「忠義」だけでは国家を動かすことはできない――。
近代日本の現実が、ここにはっきりと姿を現したのです。
この西南戦争の最中、戦場の片隅でもう一つの新しい日本の姿が生まれていました。
佐賀出身の政治家である佐野常民を中心に、敵味方を問わず負傷者を救護する団体が設立されます。それが博愛社です。博愛社は、「敵であっても命は同じく尊い」という理念を掲げ、戦場で負傷兵を看護しました。この活動はのちに国際赤十字の精神と結びつき、日本赤十字社(日赤)として発展していきます。
西郷軍と政府軍が激しく戦う同じ九州の地で、「人道の芽」が静かに育っていたのです。
戦局は次第に政府軍の優勢となり、西郷軍は南下して鹿児島へと退きます。
そして、西郷隆盛は城山に立てこもり、西暦1877年(明治10年)9月24日、ついに自刃しました。
「もうここらでよかろう」――と伝えられるその言葉は、西郷隆盛の潔い生き方を象徴するものとして今も語り継がれています。西郷隆盛の死によって、武士の時代は完全に幕を閉じたのだと解釈されています。
もはや「刀」で世を動かす時代ではなく、「法」と「制度」によって国を築く時代が始まったのです。それでも、多くの人々が西郷に感じた“人としての誠”は、時代を越えて今も日本人の心に生き続けています。
1878年 紀尾井坂の変 ― 維新の三傑、去る
西暦1878年(明治11年)5月14日。
東京・紀尾井坂のあたり(現在の東京都千代田区)で、一台の馬車が静かに進んでいました。その中に乗っていたのは、明治政府の中心人物、大久保利通です。
大久保利通は薩摩藩(現在の鹿児島県)出身で、西郷隆盛や木戸孝允と並び「維新の三傑」と称えられた人物でした。彼は明治維新後、近代国家の制度づくりに尽力し、内務省を創設して鉄道や郵便、教育制度などを整備しました。彼の目指したのは、単なる改革ではなく、「日本が自らの力で列強と並び立つ近代国家となる」ことでした。
しかしその過程は決して平坦ではありませんでした。徴兵令・地租改正・廃藩置県といった近代化政策は、旧来の特権を奪われた士族層に深い不満を生んでいました。また、大久保利通にとって最大の痛恨事は、旧友・西郷隆盛との対立でした。共に「国のため」という理想を抱きながら、2人は征韓論から端を発した明治六年の政変で袂を分かち、西南戦争(西南の役)では敵味方に分かれて戦うという悲劇の結末を迎えました。西郷隆盛が城山で自刃した翌年、木戸孝允も病没し、大久保利通は維新期からの盟友を相次いで失います。西暦1878年(明治11年)時点で、大久保利通は政府内で孤高の存在となっていました。
それでも大久保は、国家の未来を思い、休むことなく働き続けました。当時の日本は、制度は整いつつも民心はまだ揺れており、士族の不満は各地にくすぶっていました。大久保は「この国を一度立て直さなければ、日本は再び分裂してしまう」と語ったと伝えられています。それは、単なる政治家のambition(野心)ではなく、国を守る父のような責任感でした。
西暦1878年(明治11年)5月14日の朝。
大久保利通は自宅を出て、赤坂仮御所(現在の迎賓館付近)へ向かう途中、紀尾井坂で待ち伏せしていた不平士族の一団に襲われました。加賀藩(現在の石川県)出身の島田一郎ら元士族の6名が、政府の政策に対する怨恨を胸に抱き、刀を振り下ろしたのです。護衛も少なく、突然の襲撃に大久保利通は「無礼者!」と一喝したといいますが、為す術なく斬殺され、その生涯を閉じました 。暗殺犯たちは逃亡は卑怯とその場で自首し、後に全員刑死しています。
大久保利通の死によって、明治政府を支えた「維新の三傑」は全員この世を去ったことになります。薩摩の西郷隆盛(1877年没)、長州の木戸孝允(1877年没)、そして薩摩の大久保利通(1878年没)――明治維新の立役者たちが次々に姿を消したのです。
だが彼らが命を賭して築いた国家の基盤の上に、次の世代のリーダーたち(伊藤博文・山県有朋・黒田清隆ら薩長出身の後継者)が台頭し、新たな国家運営を担っていくことになります。国づくりのバトンを受け取った彼らはどのように日本を導いていくのかが楽しみですね。
竹橋事件 ― 「近代国家」のひずみ
紀尾井坂の変が起こった同じ年の西暦1878年(明治11年)、皇居のそばで起きたのが竹橋事件です。竹橋は東京メトロの東西線の駅名としても有名で、今でも毎日新聞の本社や国立公文書館や東京国立近代美術館などがある場所です。
さて、この事件の概要を説明すると、西南戦争(西南の役)で勇敢に戦った近衛兵たちが、戦後の待遇に不満を抱き反乱を起こしたのです。近衛兵とは、明治天皇の身近に仕える精鋭部隊。いわば国家の中枢にいた彼らが反旗を翻したことは、政府にとって深刻な衝撃でした。
政府・軍上層部は、ただちに再発防止と軍紀粛正に乗り出しました。陸軍卿(陸軍大臣に相当)だった山県有朋は、事件の背後に自由民権運動など社会不安の影響があると考え「軍人訓戒」を発しました。そして、従来は軍の作戦立案は陸軍省内部で行われていましたが、竹橋事件後の12月に山県有朋の後任となった西郷従道(西郷隆盛の弟)の提案で参謀局を独立させ参謀本部を新設することが決まりました 。山県有朋は陸軍卿を辞任して初代参謀本部長に就任し、軍の統制強化に尽力します 。
後に、山県有朋が主導して、西暦1882年(明治15年)に「軍人勅諭」が渙発されました。文案の起草には西周が関わります。この勅諭は「忠節」「礼儀」「信義」「勇武」「質素」の5つを軍人の徳目と定め、天皇への忠誠を第一とする近代軍人の倫理を示したものです 。特に自由民権運動が高まる中で、軍人が政治運動に関与せず、あくまで国家元首たる天皇に仕える存在であることを明確に謳いました 。
竹橋事件は、近代国家日本が内包する緊張を露呈した象徴的出来事でした。武士の時代が終わり新たな統一国家を築こうとする明治政府にとって、「力による秩序維持」という課題がいかに困難であったかを物語っています。
一連の士族反乱と竹橋事件を通じて、政府は武力・軍事の運用法を模索し、ひいては言論や制度による統治への道筋を見出していくことになるのです。
士族の反乱が残したもの ― 力の時代から言論の時代へ
武力の終焉と、言論の夜明け
西暦1877年(明治10年)の西南戦争(西南の役)をもって、士族による一連の反乱は終わりを迎えました。
薩摩出身の西郷隆盛を最後の旗印としたこの戦いは、かつて武士の世を支えた人々が、時代の変化の中で自らの誇りを貫こうとした最終章でもありました。
この戦いののち、日本では「武力による抵抗」ではなく、言論によって社会を変えようとする時代が始まります。それが、のちに全国へと広がっていく自由民権運動でした。
政府の方針や社会のあり方を「言葉」で問うこと。
かつて刀を手に立ち上がった人々の志は、次の世代に受け継がれ、ペンと演説の力へと形を変えていったのです。
経済が揺れた“戦費の代償”
しかし、西南の役が残したのは精神的な転換だけではありません。
戦争を戦い抜くために、政府は莫大な戦費を必要としました。
戦局が不利になると、東京の人々の間でも「本当に負けるかもしれない」と不安が広がり、政府は資金を集めるために、次々と紙幣を発行して軍備を整えました。このとき発行されたのが、不換紙幣です。本来なら金や銀などの“本物の価値”と交換できるはずのお金ですが、この紙幣は裏付けとなる金がなく、ただの「紙の約束」にすぎませんでした。そのため、世の中にお金が出回りすぎ、結果として物価が急上昇――つまり、インフレーションが起きたのです(インフレーションが起こるメカニズムについては別稿を参照)。実際、戦争直前の通貨流通高約1億0600万円が、戦後3年で1億7000万円にまで増えたという記録もあります (約7割増、その一因が西南戦争費用約4200万円の紙幣増発でした)。
このインフレは、人々の生活にも政府の財政にも深刻な影響を与えました。
当時はすでに地租改正によって、農民が納める税は、「土地の価格」に応じた定額の金納となっていました。ところが、紙幣の価値が下がるということは同じ1円を納めても、その「実質的な価値」がどんどん目減りしてしまうということです。税収は減り、国家の財政はますます苦しくなりました。
一方で、このインフレは、都市だけでなく農村の経済構造にも影響を及ぼしました。地租が一定であったため、土地を所有する農民(地主・豪農)にとっては、価値の下がった紙幣で税を納めることができ、負担が軽くなる面がありました。反対に、土地を持たない小作農や日雇い労働者、固定給の官吏などは、生活必需品の値上がりに苦しみました。
ただし、こうした動きは単に「持つ者」と「持たざる者」の対立では語れません。村落社会では、地主層は田畑の経営だけでなく、貸し付けや救済、村の財政・学校運営などを担う存在でもありました。信用と責任を背負う立場に立った彼らは、やがて「地域の声を政治に届ける必要がある」と考えるようになります。こうして在郷地主・豪農の一部は、地域を代表する存在として自由民権運動へ参加する道を選び始めました。
自由民権運動はもとは士族の政治参加要求から始まりましたが、1880年代に入るとその主張は「地租の軽減」「集会・言論の自由」など、農民・町人を含む広い層の利益や期待を反映するようになっていきます。
士族の志と、農村社会で力をつけた豪農の責任感、そして新しい知識人層の理想が交わることで、運動はしだいに“国家のあり方”を問い直す国民的議論へと成長していったのです。
まとめ
明治維新から十数年、日本は近代国家への大きな一歩を踏み出しました。
その陰で各地に巻き起こった士族の反抗は、一見すると新政府への反逆や暴力沙汰に映るかもしれません。しかし、彼らの行動の底流には、武士としての誇りを守ろうとした人、故郷の暮らしを守ろうとした人、そして「この国をどう導くべきか」と本気で悩んだ人々の切実な思いがありました。
明治政府による新国家づくりは、多くの痛みと犠牲を伴いながら進められました。しかしその過程で日本人は一つのことに気付いていきます。――刀では国は動かせない。ならば、言葉と議論で未来を創るしかない。かくして武力の時代は終わり、次に訪れたのは自由民権運動、そして憲法と国会による政治の時代でした 。
私たちは今、平和な教室や自宅で歴史を学ぶことができます。しかし、その平穏な社会は決して偶然に成し遂げられたものではありません。激動の時代に悩み、戦い、問い続けた先人たちの選択の積み重ねによって切り拓かれた道なのです。だからこそ今、私たち自身に問われているのは――
「もし自分があの時代を生きていたら、何を守り、何のために立ち上がっただろうか?」
「そして今という時代に生きる自分は、どんな‘言葉’で未来を築こうとしているのだろうか?」
歴史とは過去の物語ではなく、未来を選ぶための鏡です。先人たちの葛藤と覚悟に思いを馳せながら、私たちもまた自らの時代の課題に向き合い、より良い日本の姿を模索していく必要があるでしょう。