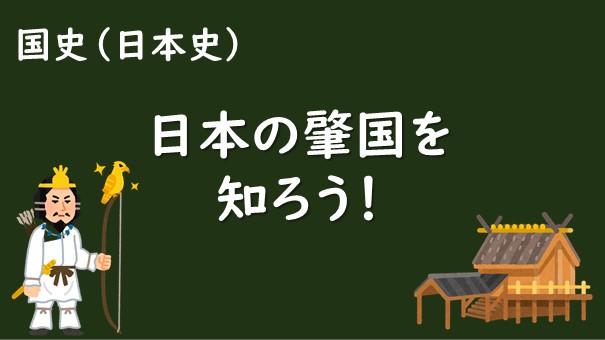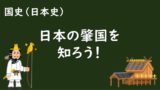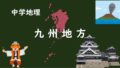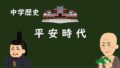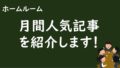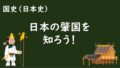今回は、「古事記」や「日本書紀」に載っている「天地初発」「天地開闢」についてわかりやすく解説していきます。
神様の名前を欲張って覚える必要はありません。覚えてほしい神様については強調してあるので、そこだけ覚えてくれたらよいです。また、「古事記」や「日本書紀」を理解する上で理解しておきたい言葉については解説をきちんと加えてあります。
さて、今回のポイントは、日本の神話に出てくる神様はどのようにお成りになっているのか?という観点を持って読んでほしい点です。
まほろば社会科研究室の日本神話に関する記述は本当に大雑把なものなので、くわしく「古事記」や「日本書紀」について勉強してみたいという人は、別で本を読んでみることをオススメします。
天地初発の際に生まれた神様 – 別天神
「古事記」の冒頭の文章です。
天地の初発の時、高天原に成りませる神の名は、天之御中主神、次に高御産巣日神、次に神産巣日神。此の三柱の神は、並びに独神と成り坐して、身を隠したまひき。
「古事記」上巻
この場面は、古事記の一番最初の「天地の初発の時」の文字をとって、一般的に「天地初発」と言います。
天地が初めて生まれたときに生まれた神様は、天之御中主神と仰います。ポイントは、キリスト教の「旧約聖書」のように神様が宇宙を作っているわけではないということです。宇宙空間があってそこで神様が成ったと書いてあるのです。なお、「どうやって宇宙が誕生したのか?」については「古事記」には一切の記載がありません。
天御中主神の次に成った神様は高御産巣日神。次にお生まれになったのは神産巣日神と仰います。神様のことは柱という単位で呼びます。3柱の神様はすぐに御身をお隠しになりました。
神様がお生まれになった場所について、高天原と書いてあります。「たかまのはら」とふりがなが振ってありますが、他には「たかまがはら」と呼んだりもします。ただ、この言葉は「古事記」の神話を理解するのに大切な舞台の1つになるので、高天原は神様が住んでいらっしゃる場所であることを頭に入れておきましょう。
3柱の神様が成った後、宇摩志阿斯訶備比古遅神が成り、続いて天之常立神が成りました。この神様も性別のない独神でした。
天御中主神、高御産巣日神、神産巣日神、宇摩志阿斯訶備比古遅神及び天之常立神は、天地が発れて早い時期に成った特別な5柱の神様ということで、別天神と呼んでいます。
神世七代が成る
その後、次々と神様が成ります。
- 国之常立神
- 豊雲野神
- 宇比地迩神/ 須比智邇神
- 角杙神 / 活杙神
- 意富斗能地神 / 大斗乃弁神
- 於母陀流神 / 阿夜訶志古泥神
- 伊耶那岐神 / 伊耶那美神
上の神様の一覧の3番目に登場する宇比地迩神と須比智邇神以降の10柱の神様は男神と女神で対になっておいでで、2柱で1代とカウントされます。
最後に成った伊耶那岐神と 伊耶那美神は、日本列島をお生みになる重要な神様です。次の物語で登場します。
ここに述べた7代の神のことを「神代七代」と呼びます。
次の物語(神話)は以下のリンク先に進んでください。