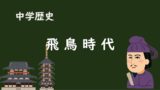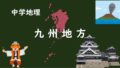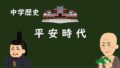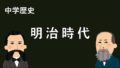聖徳太子が発案されたと言われている「十七条の憲法」の全文を一緒に読んでみましょう。
「十七条の憲法」という用語は、小学校の社会科の歴史の教科書から登場します。しかしながら、全文を解説されることはあまり多くありません。また、近代的な意味での「憲法」と比較して、「ただの役人の心構え程度しか書かれていない」といったような言説を目にすることもあります。
しかしながら、全文を読んでみると、「十七条の憲法」はこれまでの我が国を作ってきたご先祖様たちが大切にしてきた価値観そのものであり、今の時代だからこそ何かしら大切なことを感じられる内容も多く含まれています。
なお、拙稿を作成するにあたって、LearnJapan主催で国語WORKSの松田雄一先生が担当された「学んでみよう!「17条の憲法」講座 (日本が好きになる国語授業シリーズ)」の内容及び齋藤武夫先生の「日本が好きになる!歴史授業」の内容(内容はLearn Japanさんのブログに詳しく掲載)を多分に参考にさせていただきました。
この場を借りて厚く御礼を申し上げたいと思います。
- 十七条の憲法が発布された背景
- 十七条の憲法の全文を一緒に読んでいきます!
- 第一条 以和爲貴 – 和の心をもって議論をしよう!
- 第二条 篤敬三寶 – 仏法僧の3宝を篤く敬いなさい!
- 第三条 承詔必謹[しょうしょうひっきん] – 天皇からの詔書は謹んで承りましょう!
- 第四条 以禮爲本 – 礼節はとても大切です!
- 第五条 明辨訴訟 – 訴訟は公明正大にやろう!
- 第六条 懲惡勸善 – 悪を懲らしめて善を勧めなさい!
- 第七条 人各有任 – 正しい心で任務を全うしよう!
- 第八条 早朝晏退 – 仕事は準備が大切!きっちりと仕事しよう!
- 第九条 信是義本 – 信頼関係は人の道の基本です!
- 第十条 不怒人違 – 価値観の違いを認め、他人の意見を尊重しよう!
- 第十一条 明察功過 – 賞罰は功績と罪や過失をよく見て行いなさい!
- 第十二条 國非二君[一君万民] – 我が国に天皇は1人しかいません!
- 第十三条 同知職掌 – 同僚の仕事は知っておくようにしよう!
- 第十四条 無有嫉妬 – 嫉妬の心があると優秀な人材が現れません!
- 第十五条 背私向公 – 私情を挟まず公務に向かう姿勢が「和」の実現にはとても大切なのです!
- 第十六条 使民以時 – 国民を賦役する時は国民生活を考えましょう!
- 第十七条 不可獨斷 – みんなで知恵を出し合って合議の中で物事を決めましょう!
- まとめと考察
十七条の憲法が発布された背景
「十七条の憲法」が発布されたのは、西暦604年のことです。第33代の推古天皇の時代です。
「十七条の憲法」という法典が単体で残っているわけではなく、我が国の正史である「日本書紀」の中にその記述が出ています。
『日本書紀』第二十二巻 豊御食炊屋姫天皇 推古天皇十二年
夏四月丙寅朔戊辰皇太子親肇作憲法十七條
上の史料に書かれている「皇太子」というのが聖徳太子です。
聖徳太子が登場した頃の我が国の様子は以下のような状態でした。
- 国内では、第32代の崇峻天皇が蘇我馬子と対立し、東漢直駒によって暗殺される事件が起きました(西暦592年)。天皇を中心とした国の秩序は完全にはできておらず、武力や財力のある実力者が国の政治を牛耳っている状態でした。
- 我が国の近くにある中国(チャイナ)大陸に目を向けると、隋王朝が中国(チャイナ)の統一を果たし(西暦589年)、その勢力は拡大を続けていました。
要するに、国内外で政治が混乱している状態だったのです。内憂外患の状態ですね。
だからこそ、聖徳太子は、我が国の政治体制を天皇中心のものとすることで、国の政治の秩序を安定化させたかったのです。
そのため、学校の教科書レベルでの記述で申せば、家柄ではなく実力で評価する冠位十二階を定め(西暦603年)、翌年に天皇中心の政治を目指すための役人の心構えを十七条の憲法で規定したのです(西暦604年)。
政治は「よい」システムを整えるだけではダメです。システムを運用する人が「よい」状態にならなければうまく世の中は回っていきません。社会システムとはそういうものです。「十七条の憲法」は、政治システムを運用する「人」に向けて出されたものだという点を理解しておくべきです。
学習参考書などの中に「十七条憲法は服務規程が書かれている」と説明されているものもありますが、後述するように、服務規定は書かれていません。「憲法」と書かれてはいるものの、これは天皇を中心として国を1つにまとめるために公務員としての理想を述べた文章だという理解はきちんとしておくべきです。
「十七条の憲法」は、儒学的な考え方や仏教の考え方の影響を強く受けていると言われています。
細かい話になりますが、「十七条の憲法」は、「じゅうしちじょうのけんぽう」と呼ぶ方が望ましいです。「なな」という読み方は聖徳太子の時代には存在しなかったためです。したがって、「しち」と呼んだ方がより適切かと思われます。
十七条の憲法の全文を一緒に読んでいきます!
この章は、「日本書紀」の原文とその書き下し文、現代語試訳で構成します。
実は書き下し文は人によって様々です。いろいろな解説書を読んでも実は微妙な部分で異なっています。また、原文は句読点や返り点などは一切振られていません。したがって、拙稿もあくまで参考の1つとして読んでいただけると幸いです。
第一条 以和爲貴 – 和の心をもって議論をしよう!
原文
一曰 以和爲貴 無忤爲宗 人皆有黨 亦少達者 以是 或不順君父 乍違于隣里 然上和下睦 諧於論事 則事理自通 何事不成
書き下し文
一に曰く、和を以て貴しとなし、忤うこと無きを宗とせよ。人みな党あり、亦た達れるもの少なし。是を以て、或いは君父に順わず、また隣里に違う。然れども、上和ぎ下睦びて、事を論うに諧うときは、即ち事理自ずから通ず。何事か成らざらん。
現代語試訳
1つ目に訓示します。
和という概念を大切にしましょう。そして和という概念を外すことのないようにすることが大切です。人はみんなグループを作りたがるものであり、また悟りのある人格者は少ないものです。だから、主君や父親にしたがわなかったり、ご近所さんともうまくいかないのです。しかしながら、上の立場に立つ者が調和を理想として下の立場の者も仲良くしてあれこれと議論をすれば、物事の道理はおのずから通じるようになり、どんなことでもうまくいくようになるものです。
第二条 篤敬三寶 – 仏法僧の3宝を篤く敬いなさい!
原文
二曰 篤敬三寶 三寶者佛法僧也 則四生之終歸 萬國之禁宗 何世 何人非貴是法 人鮮尤惡 能敎従之 其不歸三寶 何以直枉
書き下し文
二に曰く、篤く三寶を敬え。三寶とは佛・法・僧なり、則ち四生の終歸、萬國の極宗なり。何れの世、何れの人か是の法を貴ばざる。人、尤だ惡しきもの鮮し、能く敎えば之に従う。其れ三寶に歸せずんば、何を以てか枉れるを直さむ。
現代語試訳
2つ目に訓示します。
3つの宝を大切にしましょう。3つの宝とは、仏教、仏法そしてお坊さんです。すべての生き物は最終的には仏教に帰依していくものであり、仏教は全ての国において通じる極めて優れた教えです。どのような世の中であったとしても、どのような人であったとしても、仏教の教えは尊んでいくものなのです。人間にはとてつもない悪人はほとんどいないものです。したがって、きちんと仏教の教えを身につければよい人格に育つものです。だから、仏教や仏法やお坊さんを大切にして仏教の教えに帰依しなかったら、どうやって曲がった心を直すことができましょうか。
第三条 承詔必謹[しょうしょうひっきん] – 天皇からの詔書は謹んで承りましょう!
原文
三曰 承詔必謹 君則天之 臣則地之 天覆臣載 四時順行 萬気得通 地欲覆天 則至壊耳 是以君言臣承 上行下靡 故承詔必愼 不謹自敗
書き下し文
三に曰く、詔を承けては必ず謹め。君をば則ち天とし、臣をば則ち地とす。天覆いて地載せて四時順行し、萬気通うを得。地天を覆さむと欲するときは、則ち壊るるに致るのみ。是を以て、君言えば、臣承り、上行えば下靡く。故に、詔を承けては必ず慎め。謹まずんば自ら敗れん。
現代語試訳
3つ目に訓示します。
天皇から詔書を賜ったときは、必ず謹んでそれに従いなさい。君主とは天であり、臣下は地にあたります。天が地を覆い、地は天を載せます。このようにすれば、春夏秋冬と季節は正しく巡るように全てのことがうまくいくのです。しかし、地が天を覆うとすれば(=臣下が君主をひっくり返そうとすれば)、整った秩序は壊れていきます。そういうわけで、天皇が仰ることに臣下は謹んで従うようにしましょう。上の立場の者(=上級公務員・上司)がこれを実践すれば、下の立場の者(=下級公務員・部下)もこれに倣うものです。したがって、天皇から詔書を賜ったときは、必ず謹んでこれに従いなさい。謹んでこれに従わなければ、自然と国は滅んでいくことになるでしょう。
第四条 以禮爲本 – 礼節はとても大切です!
原文
四曰 群卿百寮以禮爲本 其治民之本要在禮乎 上不禮而下非齊 下無禮以必有罪 是以 群臣禮有 位次不亂 百姓有禮 國家自治
書き下し文
四に曰く、群卿百寮、禮を以て本と爲よ。其れ民を治むるの本は、要ず禮に在り。上禮あらざれば下齊わず、下禮なければ必ず罪あり。是を以て、群臣禮あるときは位次亂れず、百姓禮あれば、國家自ら治まる。
現代語試訳
4つ目に訓示します。
政府高官や一般の公務員の皆さんは、礼節を大切にしましょう。国民を治める基本は礼節にあります。上に立つ者に礼節がなければ下々の秩序は乱れ、下の者に礼節がないときは必ず罪を犯す者があらわれます。それだから、上下の公務員に礼節があるときは社会の秩序は乱れません。多くの国民たちに礼節があれば、国家は自然と治まるものです。
関連古典
子曰
道之以政 齊之以刑 民免而無恥
道之以德 齊之以禮 有恥且格
「論語」為政第二 3
第五条 明辨訴訟 – 訴訟は公明正大にやろう!
原文
五曰 絶饗棄欲 明辨訴訟 其百姓之訟 一百千事 一日尚爾 況乎累歳 頃治訟者 得利爲常 見賄廳讞 便有財之訟 如石投水 乏者之訴 似水投石 是以貧民 則不知所由 臣道亦於焉闕
書き下し文
五に曰く、餮を絶ち、欲を棄てて、明らかに訴訟を辨めよ。それ百姓の訟、一日に千事あり。一日すら尚爾り、況んや歳を累ぬるをや。頃、訟を治むる者、利を得るを常となし、賄を見て讞を廳く。便ち財ある者の訟は、石を水に投ぐるが如く、乏しき者の訴は、水を石に投ぐるに似たり。是を以て、貧しき民は則ち由る所を知らず。臣の道亦焉に闕く。
現代語試訳
5つ目に訓示します。
公務員の皆さんは賄賂を決して受け取らず、また賄賂を受け取りたいという欲望を捨て、公明正大に訴訟を処理しましょう。国民の訴えは1日に大量にあります。1日ですらたくさん訴訟があります。ましてや、年を重ねたら訴訟は膨大なものになるでしょう。この頃、訴訟に携わる者が賄賂を受け取ることが当たり前になっていて、賄賂の中身を見て判決を出しているようです。すなわち、裕福な者の訴えは石を水に投げこむようなもので容易に訴えの内容を聞き入れてもらえます。一方、貧しい者の訴えは水を石に投げ込むのに似て、訴えの内容を聞き入れてもらえません。このために、貧しい者にとってはよりどころがなくなっています。そうしたことは役人のあるべき姿として間違っています。
第六条 懲惡勸善 – 悪を懲らしめて善を勧めなさい!
原文
六曰 懲惡勸善 古之良典 是以无匿人善 見悪必匡 其諂詐者 則爲覆二國家之利器 爲絶人民之鋒劔 亦佞媚者 對上則好説下過 逢下則誹謗上失 其如此人 皆无忠於君 无仁於民 是大亂之本也
書き下し文
六に曰く、惡を懲し善を勸むるは、古の良典なり。是を以て人の善を匿すことなく、悪を見ては必ず匡せ。それ諂い詐る者は、則ち國家を覆す利器たり、人民を絶つ鋒剣たり。亦佞り媚る者、上に對しては則ち好みて下の過ちを説き、下に逢ては則ち上の失ちを誹謗る。それ此の如きの人は、皆君に忠なく、民に仁なし。これ大亂の本なり。
現代語試訳
6つ目に訓示します。
悪を懲らしめて善を勧めることは、古くからのよいしきたりです。ですから、人の善い行いは匿すことなく、悪い行いを見たら必ず正しましょう。媚びへつらって嘘偽りを言う者は、結局のところ国家を転覆する武器であり、国民を傷つける鋭い剣なのです。また、美辞麗句を並べて巧みに話して媚びへつらう者は、上の立場にある者に対しては下の立場にある者の過失を説き、逆に下の立場の者と逢った時には上の立場にある者の過失について悪口を言うものです。このような人はみんな君主に対して忠義の心はなく、国民に対して思いやりの心を持つことはありません。これは国家の大きな乱れのもとになります。
第七条 人各有任 – 正しい心で任務を全うしよう!
原文
七曰 人各有任 掌宜不濫 其賢哲任官 頌音則起 奸者有官 禍亂則繁 世少生知 剋念作聖 事無大少 得人必治 時無急緩 遇賢自寛 因此國家永久 社禝勿危 故古聖王 爲官以求人 爲人不求官
書き下し文
七に曰く、人には各任あり。掌ること宜しく濫れざるべし。其れ賢哲官に任ずれば、頌音則ち起り、奸者官を有つときは、禍亂則ち繁し。世に生れながら知るもの少なし、剋く念うて聖と作る。事大少となく、人を得れば必ず治まり、時急緩となく、賢に遇えば、自ずから寛なり。此れに因りて國家永久にして、社稷危きことなし。故に古の聖王は、官の爲に人を求め、人の爲に官を求めず。
現代語試訳
7つ目に訓示します。
人にはそれぞれの任務があります。取り扱う職務については権限濫用をしてはいけません。優秀な者が任務を行えば賞賛の声が聞かれます。しかしながら心の正しくない者が任務を行えば世の中は頻繁に乱れます。世の中には生まれながらにして優れている人は少ないですが、よくよく心に刻みながら聖人になっていくものなのです。事の大小に関わらず、優秀な者が任務を与えられれば必ずよく治まるものです。時代の緩急に関係なく、優秀な人が現れれば自然とゆとりのあるのびやかな社会になるものです。これによって、国家は永久に危機に陥ることはないでしょう。だから昔の立派な王様は官職に適した人を与えますが、人のために官職を設けることはありません [適材適所]。
第八条 早朝晏退 – 仕事は準備が大切!きっちりと仕事しよう!
原文
八曰 群卿百寮 早朝晏退 公事靡監 終日難盡 是以 遲朝不逮于急 早退必事不盡
書き下し文
八に曰く、群卿百寮、早く朝り晏く退け。公事は監靡く、終日にても盡し難し。是を以て、遲く朝れば急に逮ばず。早く退れば必ず事盡さず。
現代語試訳
8つ目に訓示します。
公務員の皆さんは朝早くから出勤して夕方遅くなってから退勤しましょう。公務が途切れることはなく、1日中働いても全てを終えることはできません。したがって遅く出勤したのでは至急の対応ができません。また早く退勤したらきちんと仕事をやり尽くすことはできないのです。
第九条 信是義本 – 信頼関係は人の道の基本です!
原文
九曰 信是義本 毎事有信 其善悪成敗 要在于信 群臣共信 何事不成 群臣无信 萬事悉敗
書き下し文
九に曰く、信は是れ義の本なり。事毎に信あれ。其れ善悪成敗、要、信にあり。群臣共に信あるときは、何事か成らざらん。群臣に信なくんば、萬事悉く敗れん。
現代語試訳
9つ目に訓示します。
信頼とは人の道の根本です。何事にも信頼がなければなりません。事の良し悪しや成功や失敗は必ず信頼のあるなしにかかっています。公務員の皆さんが共に信頼関係があるときは、どんな難しいことがあってもできないことはありません。逆に公務員の皆さんに信頼関係がなければ、どんなことであってもみんな失敗するでしょう。
関連古典
子貢問政
子曰足食足兵民信之矣
子貢曰必不得已而去於斯三者何先
曰去兵
子貢曰必不得已而去於斯二者何先
曰去食自古皆有死民無信不立
「論語」顔淵第十二より
第十条 不怒人違 – 価値観の違いを認め、他人の意見を尊重しよう!
原文
十曰 絶忿棄瞋 不怒人違 人皆有心 心各有執 彼是則我非 我是則彼非 我必非聖 彼必非愚 共是凡夫耳 是非之理 詎能可定 相共賢愚 如鐶无端 是以 彼人雖瞋 還恐我失 我獨雖得 從衆同擧
書き下し文
十に曰く、忿を絶ち瞋を棄て、人の違うを怒らざれ。人皆心あり、心各執るところあり。彼是とすれば則ち我は非とし、我是とすれば則ち彼は非とす。我必ずしも聖に非ず。彼必ずしも愚に非ず。共に是れ凡夫のみ。是非の理、詎んぞ能く定むべき。相共に賢愚なること、鐶の端なきが如し。是を以て、彼の人瞋ると雖も、還って我が失を恐れよ。我獨り得たりと雖も、衆に從いて同じく擧え。
現代語試訳
10番目に訓示します。
心の中でモヤモヤした憤りをなくし、それを表情に出すようなことはしないようにして、人が一人一人異なる価値観を持っていることに怒ってはいけません。
そもそも、人にはみんな心があり、人はそれぞれの価値観に基づいて行動するものです。だから、他人が正しいと思っても自分は正しくないと思ったり、逆に自分が正しいと思っても他人は正しくないと思う場合があります。自分が必ず正しいというわけではありませんし、他人が必ずしもバカだというわけではありません。両方とも普通の人なのです。よいか悪いかという判断はよくよく考えて決めるべきなのです。自分も他人も共に立派な存在であるとともにバカな存在であることは、金輪に端がないのと同じようなもの(イアリングのような物を想像しよう)です。
こういうわけで、目の前の人が怒りの表情をふくませていたら、まずは自分が間違っているのではないかと考えてみなさい。また、自分一人で「コレだ!」と思ったとしても、みんなの意見を聞きながら歩調を合わせて行動するようにしなさい。
関連古典
人間は煩悩を捨てきれない存在でありそれを自覚して過ごしていこうといこうという話については、のちの鎌倉仏教で登場した親鸞なども同じようなことを述べています。
第十一条 明察功過 – 賞罰は功績と罪や過失をよく見て行いなさい!
原文
十一曰 明察功過 賞罰必當 日者賞不在功 罰不在罪 執事群卿 宜明賞罰
書き下し文
十一に曰く、功過を明らかに察して、賞罰必ず當てよ。日者、賞は功に在てせず、罰は罪に在てせず。事を執る群卿、宜しく賞罰を明らかにすべし。
現代語試訳
11番目に訓示します。
公務員の人事査定は、功績と過失をよく見て賞罰を必ず行うようにしなさい。
この頃、賞が功績をもとに与えられなかったり、罰を受けるほどの罪を犯していないのに罰が科されることがあるようです。人事査定を担当する公務員はどうか賞罰の根拠を明らかにして業務にあたるようにしなさい。
第十二条 國非二君[一君万民] – 我が国に天皇は1人しかいません!
原文
十二曰 國司國造 勿斂百姓 國非二君 民無兩主 率土兆民 以王爲主 所任官司 皆是王臣 何敢與公賦斂百姓
書き下し文
十二に曰く、國司、國造、百姓に斂めとること勿れ。國に二君非く、民に両主なし。率土の兆民、王を以て主と爲す。任ずる所の官司は皆是れ王臣なり。何ぞ敢えて公と與に百姓に賦斂せんや。
現代語試訳
12番目に訓示します。
国司や国造といった中央から地方に派遣された役人は国民から勝手に税金をとってはいけません。我が国に君主は2人いませんし、国民の側からしても2人の君主はいません [一君万民]。我が国には多くの国民がいますが、天皇が我が国の主人なのです。国司や国造といった中央から地方に派遣された公務員は天皇から任命を受けた身分なので、全員天皇の臣下なのです。それにもかかわらず、どうして税金と一緒に国民から私的に金品を収奪するのでしょうか。
第十三条 同知職掌 – 同僚の仕事は知っておくようにしよう!
原文
十三曰 諸任官者 同知職掌 或病或使 有闕於事 然得知之日 和如曾識 其以非與聞 勿防公務
書き下し文
十三に曰く、諸の官に任ずる者は同じく職掌を知れ。或は病み、或は使して、事を闕くことあらん。然れども、知ること得るの日には、和すること曾て識れるが如くせよ。其れ與り聞くこと非しというを以て、公務を妨ぐること勿れ。
現代語試訳
13番目に訓示します。
公務員の皆さんは同僚の仕事の内容を知っておくべきです。例えば、同僚が病気になったり出張で公務を休むこともあるでしょう。しかし、その同僚が職場に戻ってきた日には和の精神ですぐに仕事の引き継ぎをできるようにし、その仕事をあたかもずっと行っていたかのようにするようにしましょう。だから、同僚が不在の時に「それは自分の仕事ではありません [担当者は不在です]」と言って、公務を妨げることをしてはいけません。
第十四条 無有嫉妬 – 嫉妬の心があると優秀な人材が現れません!
原文
十四曰 群臣百寮 無有嫉妬 我既嫉人 人亦嫉我 嫉妬之患 不知其極 所以 智勝於己則不悦 才優於己則嫉妬 是以 五百之乃今遇賢 千載以難待一聖 其不得賢聖 何以治國
書き下し文
十四に曰く、群臣百寮、嫉妬有ることなかれ。我既に人を嫉むとき、人亦た我を嫉む。嫉妬の患、其の極を知らず。所以に、智己に勝るときは則ち悦ばず、才己に優るるときは則ち嫉み妬む。是を以て、五百にして乃ち賢に遇うとも、千載にして以て一の聖を待つこと難し。其れ賢聖を得ずんば、何を以てか國を治めん。
現代語試訳
14番目に訓示します。
公務員の皆さん、嫉妬の心は持たないようにしなさい。自分が他人を妬めば、他人も自分を妬みます。嫉妬の憂いは際限ないものです。ですから、知識が自分よりも勝っているところがあっても評価せず、才能が自分よりも優れていると思っても嫉妬するのです。そうであれば、500年経ってあなたが賢い人に遇うことも、また1000年経って1人の立派な人に遇うことも難しいのです。賢い人や立派な人がいなくて、どうやって国を治めることができましょうか。
第十五条 背私向公 – 私情を挟まず公務に向かう姿勢が「和」の実現にはとても大切なのです!
原文
十五曰 背私向公 是臣之道矣 凡人有私必有恨 有憾必非同 非同則以私妨公 憾起則違制害法 故初章云 上下和諧 其亦是情歟
書き下し文
十五に曰く、私に背きて公に向うは、是れ臣の道なり。凡そ人、私あれば必ず恨あり、憾みあれば必ず同ぜず。同ぜざれば則ち私を以て公を妨ぐ。憾み起こるときは則ち制に違い法を害う。故に初章に云わく、上下和諧せよ。其れ亦た是の情なるか。
現代語試訳
15番目に訓示します。
私情を公務に持ちこまないことは、臣下として大切なことです。一般的に人は私情を挟むとそこに恨みの感情が出てきます。恨みの感情が出てくれば周囲との協調はできません。周囲と協調できなければ、私情で公務を行うことになって公務を妨げることになります。恨みの心が起これば、制度に違反して法を破ります。だから、「十七条の憲法」の第1条で「和という概念を大切にしましょう」と述べたのは、それもまたこういう趣旨だからなのです。
第十六条 使民以時 – 国民を賦役する時は国民生活を考えましょう!
原文
十六曰 使民以時 古之良典 故冬月有間 以可使民 從春至秋農桑之節 不可使民 其不農何食 不桑何服
書き下し文
十六に曰く、民を使うに時を以てするは、古の良き典なり。故に冬の月には間あり、もって民を使うべし。春より秋に至るまでは、農桑の節なり。民を使うべからず。それ農さざれば何をか食い、桑せずば何をか服む。
現代語試訳
16番目に訓示します。
「国民を労役に徴用するには時期を考えよう」という考えは昔からのよい教えです。ですから、冬の季節には暇ができるので、その時に国民を動員するようにしましょう。春から秋までは、農作業や養蚕に力を入れる季節です。ですから、国民を動員してはいけません。農業がなければ何を食べ、養蚕をしなければどうやって服を着るというのでしょうか。
第十七条 不可獨斷 – みんなで知恵を出し合って合議の中で物事を決めましょう!
原文
十七曰 夫事不可獨斷 必與衆宜論 少事是輕 不可必衆 唯逮論大事 若疑有失 故與衆相辮 辭則得理
書き下し文
十七に曰く、夫れ事は独り断ずべからず。必ず衆と與に宜しく論うべし。少事は是れ輕し。必ずしも衆とすべからず。唯、大事を論うに逮びては、若し失有らんことを疑う。故に、衆と與に相辮ずれば、辭すなわち理を得ん。
現代語試訳
17番目に訓示します。
物事は一人で決めてはいけません。必ずみんなで議論して判断しなさい。些細なことは大したことはないので一人で決めても構いません。しかし重大なことを議論する場合には、過失によって判断を誤ることを疑いなさい。したがって、みんなで議論を尽くせば、道理にかなった決断を下すことができましょう。
まとめと考察
感想
十七条の憲法をこのように読んでみると、現代社会でも大きな示唆を与える内容ですね。道徳の本として、あるいはビジネス書として読んでも早速自分の生活に取り入れたくなる内容です。
個人的に強く印象に残るのは議論の進め方について述べられた条文です。第1条や第10条や第15条や第17条の条文を繋いで読んでみると、「和」を大切にしようというところから議論のマナーのような内容が書かれています。今から1400年以上も前の日本で既にこういったことを目指そうとしていたことが史料から分かります。
翻って現代社会の様子を見ると、インターネットの言論空間では好き勝手に「和」を大切にしない発言が目立っています。聖徳太子が大切にしようと考えていたことを見つめてもよいのではないかと考えます。そして、自分自身も気を付けていかねばならないと感じます。
話し合いによって…という点は、「古事記」や「日本書紀」においても神様が何度も話し合いをするシーンが登場しています。また、先の大戦の後に昭和天皇が渙発された「新日本建設の詔」の冒頭で「五箇条の御誓文」を引用したところからも分かるように、日本の国づくりのアイデンティティが「話し合い」であるという点は特筆に値すべきことであると考えます。
「十七条の憲法」は、この他の条文を読んでも学べることが大変多く、何度も読み返したい文章だと思います。
「17」という数字について
古来から、日本では「17」という数字を神聖化しているようにすら見えます。そもそも、日本を生み出した神様の数も17です(別天津神と神世七代を合わせると17になります)。
他にも、以下のような法令の条文数に影響を与えています。
- 飛鳥時代の末期に文武天皇の御代に発布された「大宝律令」→17巻で構成されています。
- 鎌倉時代に執権の北条泰時によって作られた「御成敗式目 [貞永式目]」→51条(17条×3)で構成されています。
- 室町時代に足利尊氏によって作られた「建武式目」→17条で構成されています。
- 江戸時代に徳川幕府によって作られた「禁中並公家諸法度」→17条で構成されています。
- 大日本帝国憲法の「第1章 天皇」の規定→17条で構成されています。
これらの法令は「十七条の憲法」の影響を受けて…と説明がされているものもありますが、少なくとも「日本書紀」が編纂された頃の日本では既に「17」という数字が神聖化されていたと解する方が妥当な気がします。
十七条の憲法は現代社会に生きる人にとってのバイブルになり得る
このように「十七条の憲法」を見てくると、現代社会に生きる私たちにとっても学ぶべきことがとても多い内容だなと感じます。ビジネス書では孫子の「兵法」や孔子の「論語」などを題材にしたものがありますが、「十七条の憲法」をモチーフにしたビジネス書はあまり見かけません。
同胞の大先輩が作られた古典をもっと大切にしていきたいものです。
執筆者: