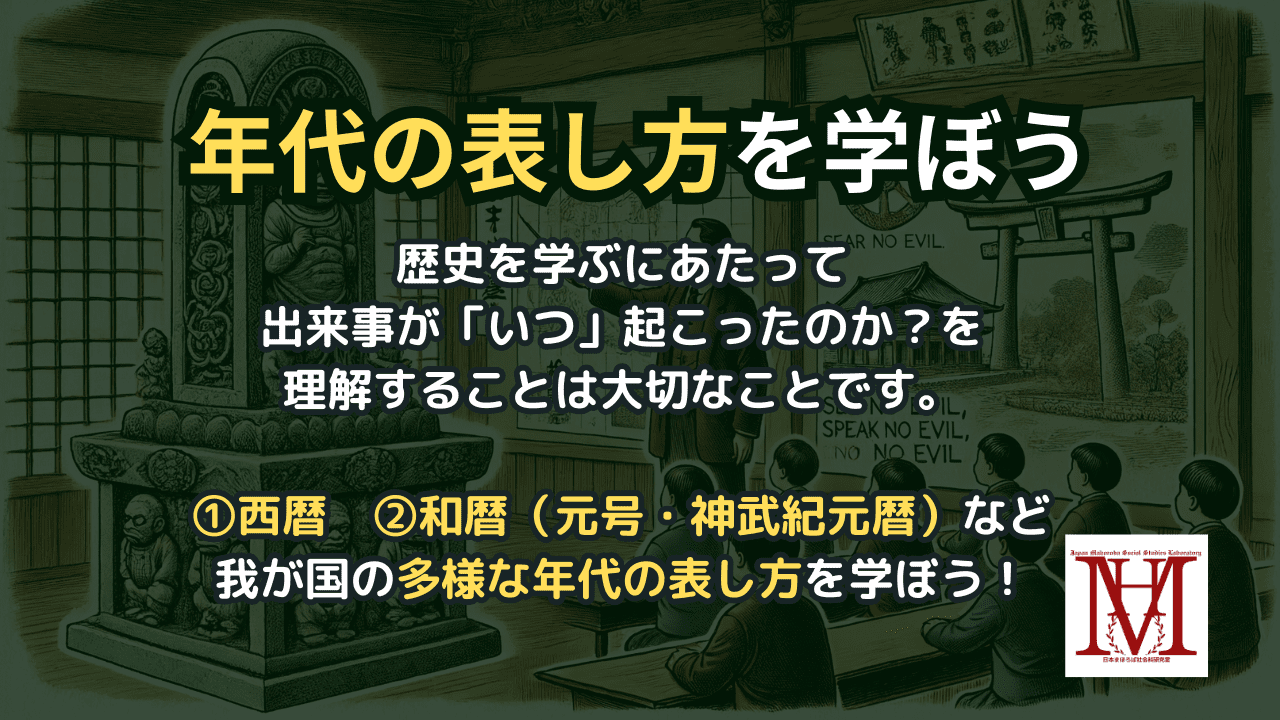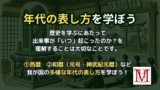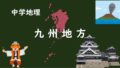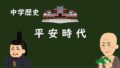歴史の勉強で大切なのは、いつ?どこで?何が?どのように起こったのか?を理解することです。特に大切なのが、いつ起こったのか?を理解することです。これは年代をどのように数えるのか?という問題につながっていきます。
年代の数え方のことを、難しい言葉で、紀年法と言います。
今回は年代のカウントの仕方のパート1ということで、西暦と世紀について勉強していきます。
西暦とは何? – その意味を学ぼう!
現在の日本では、「西暦」は「和暦」と併用して使われています。
西暦とは、イエス・キリストが生まれたとされる年を1年(元年)と定める暦のことです。敢えて「イエス・キリストが生まれた【とされる】」と書きました。ホントかどうか分からないからです。生年月日がデタラメだという説もあります。でもみんな使っているからそのまま使っているといってもよい感じです。生まれた年を0(ゼロ)年にしていないのがポイントですね。
イエス・キリストが生まれる前の年は「紀元前(B.C.)○○年」と表します。B.C.はBefore Christ(ビフォー・キリスト)の略です。
これに対してイエス・キリストが生まれた以降のことを「紀元」または「紀元後」と言い、通常は省略されます。アルファベットではA.Dと言います。これは英語ではありません。ラテン語のAnno Dominiの略です。アンノ・ドミニと読みます。アンノは年、ドミニは主(キリスト)のという意味です。
今では世界で使われる年代の表し方になりました。日本でも多く使われていますね。
世紀とは? – 数え方で気をつけたいポイントも紹介!
さて、西暦では100年区切りで1まとめにする数え方があります。これが「世紀」です。英語ではcentury(センチュリー)と言いますね。cent-の部分は100分の1という意味。長さの単位のセンチメートルのセンチも同じ100分の1という意味。1mの100分の1が1cmです。小学校の時に1メートルは100センチメートルだと習いましたがこれも同じ考え方です。外国の通貨でも「セント」という単位が使われます。1ドルは100セント(cent)です。これは1ドルの100分の1が1セントだからです。
さて話を進めると、西暦は1年から始まっていますから100年ごとに区切るということは、
「1世紀=西暦1年から西暦100年まで」ということになりますね。
ではこんな問題はどうでしょう?なんとこのような問題がお茶の水女子大学という名門大学の入試問題で出題されたことがあります。
「関ケ原の戦い」が起こったのは何世紀ですか?
「関ヶ原の戦い」は、西暦で言うと1600年に起こりました。ちなみに、和暦の元号で表すと、慶長5年です。
これを「世紀」で表してみましょう!
「西暦1501年から西暦1600年までが16世紀」になりますよね。したがって16世紀が正解です。
西暦から世紀へ変換する場合、古典的なやり方としては、西暦の上2ケタの数字に1を加えると世紀になるというやり方があります。
(例)1728年は何世紀か?
1728の上2桁が17。これに1を足すと18。だから18世紀というやり方ですね。
ただ欠点もあります。西暦1600年を世紀に直す場合、上二桁が16→だから1を足して17世紀とやると間違いです。答えは先ほどもやった通りで16世紀。16世紀は1501年から1600年までで、17世紀は1601年からスタートだからです。下2桁が00の場合は上2桁に1を足してはいけないのです。
西暦から世紀へ変換するやり方は他にもありますよ!ネットで調べてみると、100円玉だけでの買い物をするという例で世紀から西暦へ変換するやり方を説明しているサイトがありました。面白いですね。
(例)西暦1728年は何世紀か?
まず1728年を1728円と置き換える。1728円の品物を100円玉だけでお買い物をするシーンを考えます。では100円玉は何個必要か?と言われれば、100円玉は18枚必要です。だから18世紀!って答えるという感じです。分かりやすくていいですね。

このやり方ですと、先ほどの下2桁が00の場合でも説明が付きますよね。
西暦1600年→1600円→1600円の品物を買い物する場合100円玉は何枚必要か?→16枚→16世紀
これだと引っかからないですね。ネットの記事を読んでいてとても勉強になりました。
まとめ – 西暦が当たり前になっている世の中だからこそ和暦の存在意義を考えよう!
今回は、日本でも一般的に使われるようになった西暦や世紀といった欧米の紀年法について学習しました。
しかし日本には元号や六十干支などといった紀年法も存在します。
最近、和暦を廃止して西暦のみを使うべきだという意見が多く出るようになっていますが、それは適切だとは思いません。和暦は日本でしか使いません。世界はグローバル化していると言われていますが、世界の中のダイバーシティーを保全するためにも、我が国のオリジナリティはそのまま出せばよいのです。西暦も和暦もTPOに応じてコーディネートして使える方が文化として成熟しているように思いますが、皆さんはいかがでしょうか?ぜひ和暦編もよろしくお願いします!