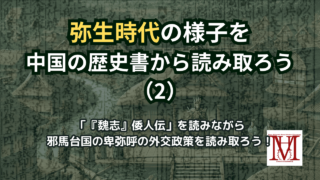 歴史
歴史 「魏志倭人伝」から見た弥生時代 – 邪馬台国の卑弥呼
「魏志倭人伝」から見た弥生時代(日本)の様子をわかりやすく解説します。卑弥呼や邪馬台国が登場します。我が国の肇国の歴史とどのような関係があるのでしょうか?今回は、卑弥呼の家来の立場に立って卑弥呼の政策選択の悩みを聞いてもらう政策選択発問を設けました。
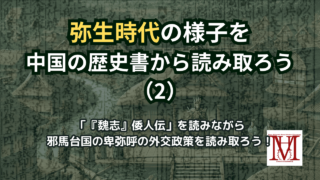 歴史
歴史 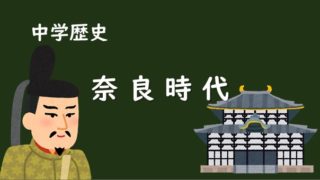 歴史
歴史 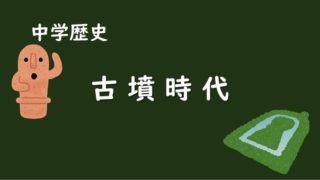 歴史
歴史 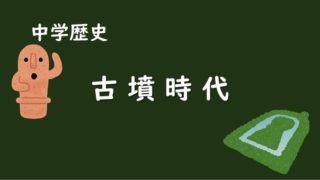 歴史
歴史 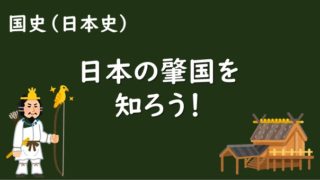 記紀における日本の肇国
記紀における日本の肇国 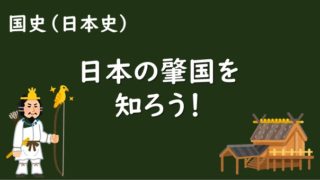 記紀における日本の肇国
記紀における日本の肇国 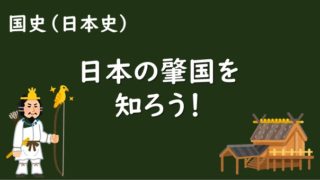 記紀における日本の肇国
記紀における日本の肇国 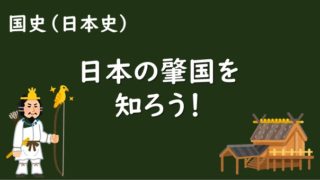 記紀における日本の肇国
記紀における日本の肇国 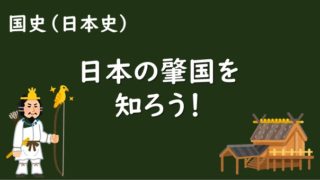 記紀における日本の肇国
記紀における日本の肇国 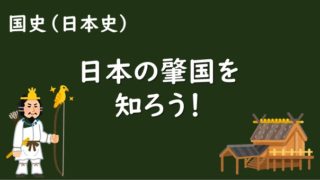 記紀における日本の肇国
記紀における日本の肇国