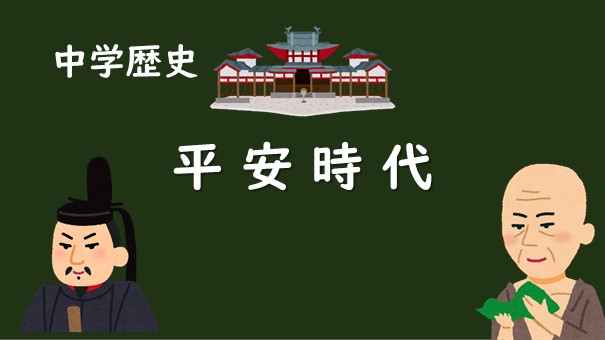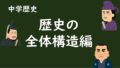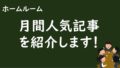奈良時代に墾田永年私財法が制定されてからできた荘園の影響で公地公民制がほころびを見せ始め(奈良時代の土地制度の変遷についてはこちら)、平安初期において桓武天皇や嵯峨天皇の治世で公地公民制の立て直しを図りました(平安期初期の桓武天皇の政治についてはこちら)。
さて、これらの改革がうまくいったのかというと、結論から言えばうまくいきませんでした。
今回は、平安時代の中期から増えてきた寄進地系荘園と呼ばれる荘園について、なぜ日本に拡がっていったのか?どのようなものなのかについてわかりやすく解説していきたいと思います。
寄進地系荘園の誕生
西暦743年に墾田永年私財法が制定され荘園が生まれました。しかし、このタイプの荘園はまもなく消滅します。奈良時代に生まれたこのタイプの荘園のことを初期荘園というのですが、初期荘園は現場監督者である郡司(ぐんじ)が協力してくれないと機能しない仕組みなのです。要するに、公地公民制が機能しないと成り立たない仕組みだということです。
10世紀になると、班田が行われなくなりました。こうなると、空き地が増えていくイメージを想像してください。そこを力のある地方豪族や農民たちが勝手に開墾を始めます。彼らのことを開発領主と言います。郡司が絡んでいないので、朝廷は税を取り立てにくくなります。開発領主たちは脱法行為を行い、税を免れようとします。
一方、地方の政治や税の徴収は国司に任せるようになっていきます。朝廷からすれば税を取りたい。だから国司に強大な税の徴収権を与えます。すると、国司がやりたい放題になります。国司はふつうは都に住んだままなのですが、人によっては現地に赴きます。私腹を肥やすために、ノルマの分の税は都に送りますが、残りは国司の手元に残しました。多くの税負担を農民たちに強いる国司も出てきました。
そこで、開発領主たちは朝廷で力を握っていた藤原氏などに守ってもらおうと考えました。国司よりも上級貴族の藤原氏の方が偉いからです。もちろん開発領主はタダで守ってもらおうとは思っていません。彼らは藤原氏などの有力貴族や寺社に対して荘園を寄進しました。寄進というのは物品や金銭を寄付することです。荘園を寄進する方も寄進される方もウマいハナシです。こういった荘園のことを寄進地系荘園と言います。開発領主は荘官としてそのまま現地で活躍しました。
このようにして、開発領主は重税を逃れようとしたのです。税を納めなくてもよい権利のことを不輸の権、国の役人が自分たちの田んぼに入ってくるな!と言える権利のことを不入の権と言います。そして、税金のかからない田のことを不輸租田と言いますが、寄進した自分たちの田んぼを不輸租田にしていきました。一方、藤原氏などの貴族や寺社はこのように荘園を寄進されることで、経済基盤を確保してきたのです。
公領
一方で、国司(朝廷)の力がそのまま及んでいる領地のことを公領(こうりょう)と言います。
まとめ – 平安時代中期には2種類の土地があった!
平安時代の中期の日本には、荘園と公領という2種類の土地が存在していたのです。
それが、寄進地系荘園と公領だったということです。
これを荘園公領制と呼びます。この呼び名は高校の歴史の教科書で出てきます。
唐・朝鮮半島の公地公民制の崩壊の様子
律令制は唐から学び、日本流にアレンジされて導入されました。
律令のオリジナルを生んだ唐もまた地方から税が取れなくなり、地方にいる節度使(地方にいた軍の司令官)に税を徴収する権限を与え、結果として国力が弱まりました(くわしくは遣唐使の停止のコンテンツをご覧ください)。
唐の律令制を導入した新羅もまた同じようなことが起こっています。そして、唐の国力が弱くなるとともに新羅の国力も弱まります。新羅の政治体制に不満を持っていた旧高句麗人の王建という人物が新羅を倒し、高麗という国を建国しました(西暦918年)。
国内の力を結集して外敵に備えることは確かに大切ですが、国が安定するとその力を維持することが逆に難しくなっていくのだなということを感じますね。